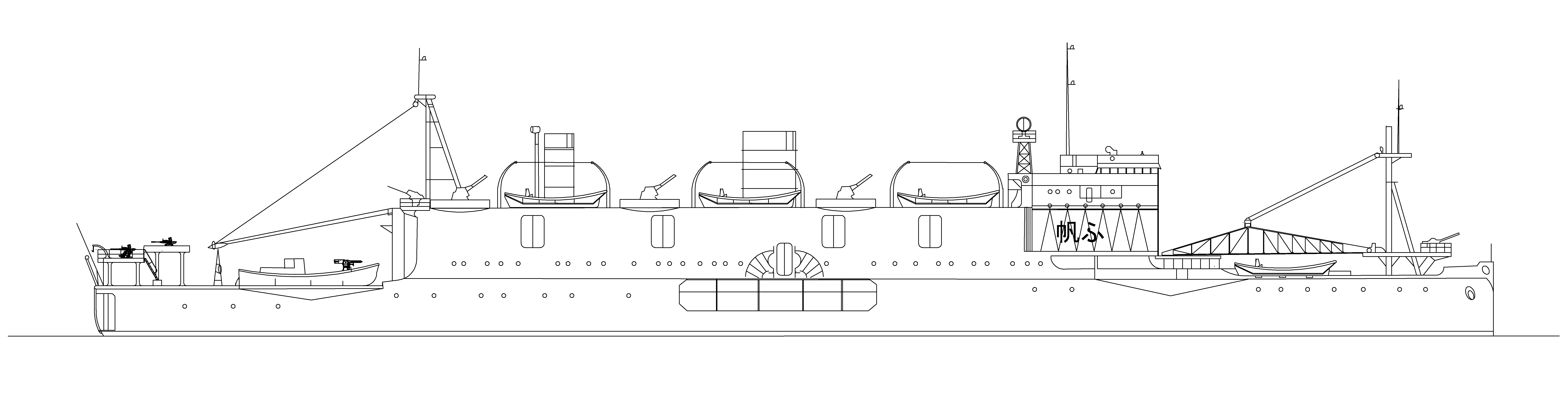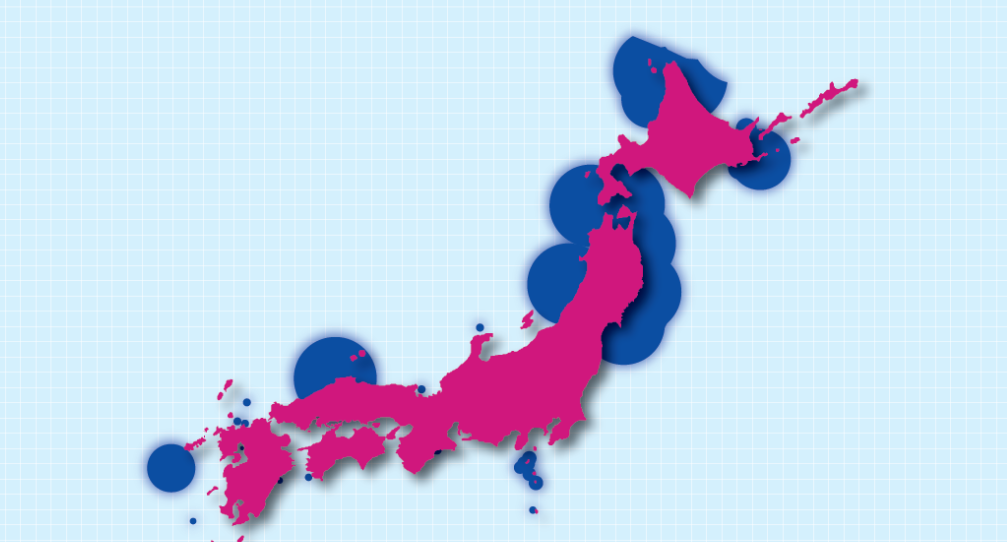�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�y�ŋ��z���d/���d��22�y�퓬�@�z YouTube����>4�{ �j�R�j�R����>1�{ ->�摜>20��
����A�摜���o �b�b
���̌f����
�ގ��X��
�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1620344980/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
!extend:checked:vvvvv:1000:512
���d�Ǝ��d�����l�@����X���b�h�ł��B
�O�X��
�y�ŋ��z���d/���d���@21�y�퓬�@�z
http://2chb.net/r/army/1618377497/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
����Ƃ����ƃ��b�`���C�t���Ō��Ă�ꂽ��
���a�ւ̎v�����p���@�|�c���̐�����A�u�}��V��v�ɂ܂��h�L�������^���[���쒆
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f48062faf088c56fb1d73fa4c4138ac1ec006e4 ��������
�@�|�c�s�Ȃǂɂ��ƁA1945�N5��5���A���C�R�퓬�@�u���d���v�ƕČR�����@B29����풆�ɋŏՓ˂����B
���d���͓��s�v�ۂ̒J�ɒė����ď��N��1�l�����S�B
�ĕ�12�l�͗����P�ŒE�o�������̂́A1�l�͎��E�A1�l�͏Z���ɎE�Q����A8�l����B��Ő��̉�U�̔팱�҂ɂ����ȂǁA�@���������S�������𗎂Ƃ����Ɠ`�����Ă���B
�ԗ��͍H����������̕����v����i�̐l�j�����Ă̋]���҂����߁A77�N�Ɍ��������B
���̐��\�ǂ�����Č��܂����H ���ẴG���W�������e�� �������v�̔w�i
https://news.nifty.com/article/item/neta/12203-106420/ �E��Z���ꍆ�͏�퓬�@�i�P�t�@�B����s��1935�N2���j
�ō����x406km/h�A�q������1200km�A7.7mm�@�e2��
�EF3F-3���t�퓬�@�i����s��1935�N3���j
�ō����x425km/h�A�q������1577km�A12.7mm�@�e1��A7.62mm�@�e1��
�EF2A�P�t�퓬�@�i����s��1937�N12���j
�ō����x489km/h�A�q������1762km�A12.7mm�@�e3��A7.62mm�@�e1��
�EB-10�����@�i�G���W��2���B����s��1932�N2���j
�ō����x343km/h�A�q������1996km�A7.62mm�@�e3��
�EB-17�d�����@�i�G���W��4���B����s��1935�N7���j
�ō����x406km/h�A�q������3218km�A12.7mm�@�e5��
�EB-18�d�����@�i�G���W��2���B����s��1935�N4���j
�ō����x348km/h�A�q������1450km�A7.62mm�@�e3��
�n�Z�K���A�v�����f���u���{�q���� �ԏ�v�{�����o�J�n�I
5/7(��) 0:00�z�M
https://news.yahoo.co.jp/articles/06595abe2dd266fe6a865b6e8f0ca07698b53b63 ���t�����Ă���͍ڋ@�i�]�����i���g�p�j�͗��21�^�A���͔��A�㎵�͍U��3��B
�c�O�Ȃ��率�d���͕t���Ȃ�
>>6 ���h�������Ƃ���q���͂�20���ቺ����Ǝ��Z���Ă���
���̎��Z�̑Ώۂ͋���50�^���A���Ȃ킿����62�^�ł���B
���52�^�͋@���R���^���N570L�ɑ��āA
���64�^�͋@���R���^���N650L�ɉ����āA�����^�^���N��60L���x(63�^�̃f�[�^)��ς�ł���͂��B
����4x��5x�Ȃ琅���^�^���N�͕s�v�Ȃ̂ŁA������R���^���N�ɏo����B
�̂ɔR����2���ȏ㑽���ς߂邽�߁A�q���������͉����\
�����o�͂����サ���u�����v�܁Z�^�i1300�n�́j�Ȃ琫�\���オ�����߂܂����A
������͑����m�푈���Ոȍ~�̓o��ŁA
���ۂɓ��ڂ�����㎮�͏㔚���@���^�́A1943�i���a18�j�N1���̓o��ł��B
����5x�̗뎮�A���@22�^�̃f�r���[��1942�N�A
96���U23�^�̓C�}�C�`�ǂ�������A
A���ɎQ�������ƌ����L�q��M����Ȃ���O�Ƀf�r���[���Ă鎖�ɂȂ邪�E�E�E
����킪���|���ꂽ�A�����J�C�R��F6F�u�w���L���b�g�v�͏�퓬�@�́A
�����̍��ɂ͎��p������Ă���
F6F�̏��w��1943�N9���A����1���f�r���[���Ƃ��Ă��Λ�����̂�F4F�B
44�N���Ղɂ͋���62�^���ڋ@���Ԃɍ�������AF6F�R�͂����܂ő҂ĂΗǂ��B
�n115�U
>>8 ���̋������ڂ̏ꍇ�͗�펎��@�ɊԂɍ������̂Ȃ̂�4���^��990�`1060�n�͂̂͂�
�ŁA�q��������������n�܂��Ă��������ɔR���𑽂��ς߂�Ƃ����̂����łɗʎY���n�܂��Ă����h��950�`980�n�͂ɑ��đ傫�ȃA�h�o���e�[�W�ɂ͂Ȃ��ĂȂ�
����\���̃o���u�A������������{�`���̋Z�p
https://motor-fan.jp/tech/10016000 ���P����o���u�͂��Ƃ��ƍq��@�p�G���W���ɗp����ꂽ�Z�p�B�ʐ^�͂��ĎO�H�d�H�ō��ꂽ�u�����v�G���W���̃V�����_�[�ƍq��@�p�̒���o���u�̈ꕔ���B�u�ΐ��v�G���W���⑼�А��G���W���ɂ��̗p����Ă����B
�m�Ǔ����n���d�����c�@�푈�͂�����c�}��q�ꂳ��@���C�R�p�C���b�g�@�P���X���A�S�s�S�Ŏ����A�X�S��
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210428-OYT1T50195/ �R��dat�����������킩���
>>8 44�N���Ղɂ͋���62�^���ڋ@���Ԃɍ������H
�Ԃɍ����ĂȂ�����44�N���Ղɋ���62�^���ڋ@�͐��ɋ��Ȃ������Ȃ�
���d���̋@���߂��ė_����n43�ɉ��C���čׂ��Ȃ����̂ɂ͏���
>>10 ���܂�A�u�����v�G���W���ւ̊����͖��Ӗ��ƍl�����܂��B
�̕����̘b������A���ƂȂ��Ă�̂͐푈���̋��������b�ł���B
�ŁA1943�N1���f�r���[�ŗǂ��Ȃ爤�m��99�͔��̗Ⴉ�猾���ċ���5X�ōs����B
�ő���O�|���Ȃ瓯���O�H��96���U23�^�Ɠ������炢�̎���(�s��)�ł��\����
>>15 �S���i��V�^���猩��1944�N8���͊Ԃɍ����B
�܂����Ղƌ����ėǂ���ˁH
>>17 ����͍̗p�̘b�ł���
��͉��Ɣz���͂��������H
>>18 ���Ƌ�����������ǂ������Ȃ�H
>>19 �S���i��V�^���猩��1944�N8���͊Ԃɍ���
�܂����Ղƌ����ėǂ���ˁH
���Č����Ă��͉̂���������H
8���ɊԂɍ������Ēf�����Ă��̂�
�S���i��V�^�̐�������͏��a19�N12�����Ǝv���Ă������A8���ɊԂɍ����Ă����Ƃ����b�͊��Ƌ��������邩��ڂ���
>>20 ��肪�Ƃ�
��������1944�N���͖������E�E�E
����5x�ɂ����邵���Ȃ���
���ܒ��ג��������ǁA�����i���1944�N�����ȁE�E�E
>>21 ����44�N8���ɊԂɍ������Ęb�����������̂�����
�������ɑz���Ǝv�����݂�44�N���{�ɊԂɍ����Ă錾���Ă�킯����Ȃ��Ǝv����
�t�B���s���������ŏ����Ǝv���Ă������A�����m��Ȃ������̉\�����邵���ʂɋ����ė~�����̂�����
>>23 ���߂�Ȃ��������̗p�̎����ƍ������܂���
�����Č����Ȃ�L46�V�̎��삪���@��Ɏ�������
�x�ꂽ�ƌ����̂��������ŗ����ǂ݂����̂�
�����i��̕����z�����̂�1944�N10��(���w��12��)����Ȃ̂�
�ŗD��ł���Ă����������O�|���o���������˂��Ē��x
>>24 �����A�Ȃ�ւ�
�O�|����]�͖������A���̎�̘b���Ĕ��邵�c�}���i�C���炱�̘b�͂����܂��ł�����
���肵��1500�n�͂�O�������ł���̂�45�N�ɂȂ��Ă���Ƃ��A���͂�o�O�Ƃ����Ă��������x��
��̓n104(�n42)���炢
���͔��������l�l�^��������l�^�ɂ��ăK�b�c���q�������������Ă邵��
96���U
�ČR���b�l�@�����ɂ���Val 22(��㎮�͔����^)��286US�K�����܂�1082L���ς߂����
>>30 >250kg���e���ڏ�Ԃł̃f�[�^��175US�K����(662L)�̂��̂����Ȃ��A���̏ꍇ965�}�C��(1553km)��s�\�Ƃ��Ă���
���ꐳ�K���
�߉�ԂȂ炻�̕ČR�̐��l�ɋ߂����炢��s�\�ŁA���ڔ��e�͖ܘ_25�Ԕ��e
���^�͔R����Ȃ��Ă��邯�ǁA����ł����^���l��2000�q�ȏ��ׂ�Ɠ��{���͌����Ă�
>>31 �������m�����
���{���̃f�[�^�Ƃ��Ēm����1050km�͐��K�S����Ԃł���Ȃ��Ƃ����b��
��͂��甭�͂ł���ő哋�ڔR���ł̐��l�Ƃ����ȁ@>�@1050km
>>33 ���ꂾ�ƃ}���A�i���̐����t���Ȃ���
���@���͑��̉��������čb�����Ƌ����͋߂��킯�ł�
�������͂ɖ߂�Ȃ��Ƃ͂����A�������U��������Ɍ����ċ߂��킯�ł͖������b�v���֒H��t����킯���Ȃ�
�O�����P-51�̌㕔���̓��R���^���N�́A
�R�������ς�ŏd���Ȃ��Ă��鎞�_�ŋ��@���Ɉ��e���^���邾�낤���ǂ�
�@�̃o�����X�Ȃ�āA�Ȃ��Ȃ�Ƃ��Ȃ����Ȃ���
�܂��P�ɐi�o������L���ړI�Ȃ�債�����ł��Ȃ��̂��ȁH
���̌㕔���̓��^���N�ɂ��ẮA���ۂ̂Ƃ����ԋC�ɂȂ��Ă�̂�
���ɋ���50�^��(62�^)���ڂ��鎖�����������Ƃ���
��(�C)�@���������ɂ��@�̕⋭��������̂�
���q���͎l���������x�U�f�ɂ��Ď��p���l�Ȃ��V���l������
��(��)�@���⋭������͍̂q���͓��@����12�m�b�g���ƂȂ�
http://www.warbirds.jp/truth/zeke.html �Ȃ��⋭������q�����������т�̂�(;�L�t�M)
�ŁE�E�E�ӂƎv�������ǁA���̋@�̕⋭����
�Ђ���Ƃ��Č㕔���̓��^���N�̐ݒu���܂ގ��Z�Ȃ̂��Ȃ��Ďv�����肵�Ă��B
���������a18�N10���Ȃ̂�52���@����Ɖ��肵��
52�^�@570L
���̑O60L�@����215L�~2�@�O��40L�~2
�⋭��������́@510L
���̑O�͐����^�^���N���@����215L�~2�@�O��40L�~2
�⋭������́H�@650L
���̑O�͐����^�^���N���@����215L�~2�@�O��40L�~2�@�㕔����140L
���傤�Ǖ⋭��������̂ƕ⋭������̂̔䗦��6��8�ɋ߂����E�E�E
�ǂ�Ȃ��납�H
���ʉd�̕ω����W���Ă���̂ł́B�������A�R���^���N�����݂������낤��
>>38 �������ڂ̜a���Ɣ�r���Ă݂ẮH
�ΐ���1939�N�ɂ͊m����1500�n�̓G���W���Ƃ��ċ����ł���łȂ��́H
>>40 �����^�t���G���W���́A�����^�����Ȃ���
���̃G���W���ƔR��債�ĕς���̂���Ȃ����m���
�Ǝv���̂ŁE�E�E
99�͔�22�^(����54�^)
>>30-31 ���K��662L�A25�ԓ��ڂ�1553km
�a��33�^(����62�^)
���K��650L�A25�ԓ��ڂ�1519km
�������(����62�^)����
���̓��^���N�lj���650L�A�T��1500km�O��H
������͗��52�^�̍q����(���K1921km)��2�����ƌ����b�Ƃ���v����
�������(����5x�^)����
�����^�^���N60L��R���^���N�ɏo����̂�
710L�A�T��1640km
���64�^(����62�^)�@���@�R�����Y�݂�[������E�E�E
max650L�A���K850km
>>41 ���d���Ēm���Ă�H
����ɋ��͂ȉΐ���O�Ƃ���1800�n�͐ς�ŁA�ΐ퓬�@�̋�퐫�\���̂Ăč����ɐU�����͂��̗��d��600km/h�͂��Ȃ����炢�߂��ፂ���\�Ȑ퓬�@
���d�̓�
>>44 �̓�
���a18�N���ɂ́A���d����̎��̎�͐퓬�@�ɂ���ƌ����b�͉���Ƃ��Ăł���b��ł͂Ȃ�
�������̒ʂ藋�d�͋�퐫�\�������A�G�퓬�@�Ƃ̋��ɎQ���o����悤�ȋ@�̂ł͂Ȃ��B
�ɂ��ւ�炸
>>44 �́A�O��������㕔���̓��^���N�Ȃ�
���d�̋r��L�����Ƒ��~��������B
�Ȃ����E�E�E
>>45 �b����̋敪�͏��a20�N�ɂȂ��Ă�����o���ꂽ���̂ŁA�����̊C�R�ɂ͊͏�퓬�@�Ƌǒn�퓬�@�Ƃ����敪
�ǒn�퓬�@�̋ǒn�Ƃ����͕̂�͂ɓ��ڂ��ċ@���o���鎖�Ɣ�r���Ă̋ǒn�Ȃ̂ŁA�K�������q���͂��Z���@�̂��w�����̂ł͂Ȃ�
�@���āA�Ȃ��A�������Ђ˂肱�ݐ�@�����l�������ƌ����܂��ƁA����͏\��N
>>46 �b��≳��͏��a18�N�ɂȂ��Ă��琶�܂ꂽ���̂ŏ��a20�N�ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ�
�����ǐ�ł����d���b��A���d������ƌ��Ȃ���Ă���
�Ȃb�̓Y�������ǁA�h��퓬�ł����Ă��q���͏��Ȃ��Ă悢�Ƃ͕K�����������Ƃ͂����A
�U�����̌�q���ēG�퓬�@�Ɛ키�悤���m�㌈��ɎQ������悤�ȔC���͊��҂���ĂȂ�
���a18�N6���̐��\�W������
>>48 ����͒m�����
��\���b��̂���ƈ���ď\�����ǐ�̍��͂܂������̎g���Ă邩�炻��͂Ȃ��Ɣ��f�������A���\�W���ɂ��̃J�e�S�����L�ڂ���킯�ˁH
>>49 �O�H�̐v�w�����○�d�̉��C�ɒǂ��Ȃ��Ƃ����O��ŗ�\�肵�Ă�����ł́H
���ۂɂ͒x��Ď���@�̏���s��19�N�t�ɂȂ��Ă��܂�����
�Ƃ��������̐��Y�I���\��͌��ǁA�������Ă��邩��Ȃ�
>>49 ��������肻���Ȃ̂́A�Ԃɍ���Ȃ������̑��ɁA�{�c�ɂȂ����w���A�V���A�M�d������
����ɒx��ċk�ԁA�H���A�k�d
���ǁA�Ԃɍ��������ɂȂ����瑼�̃o���G�[�V�����͎��d���̉����ł������
���21�^��S19�N�t�܂ō���Ă�����
1943�N4���@�����^21�^(����41�^)�A�����^22�^(52�^)�̊J���v�悪�m�F�ł���
>>54 �Ԉ�����A
1943�N8���ɂ�21�^�ɐ��͔r�C�ǂ���ꂽ��Ȃ��̂��E�E�E
�����͂��̍��_�O���X�����Ő��Y���{�ɂȂ����l������p�J�p�J����Ă�̂ɂ�
�O�H�͎O�H�ŗ��U�ɂ����ԃ��\�[�X�H���Ă�
���ɂЂ����Ă��̂�12���͐�̘b�����
21�^�A�����ƈꍆ�e��60���e���̂܂܂Ȃ狃����ȁ@
���É��H��̗A���̎�͈͂�т��ċ��Ԃ���Ȃ����������H
>>58 12���͐킷�����銊���H�������̂ɗ��U�Ȃ�
>>59 21�^�͓r������60������100���ɕς���Ă���
>>60 �펞���A�������O�H�����Y�ɕK�v�ȋ������艿�i�����Ĕ�����������Ď��Y�ɂȂ����́H ��ʐl�̔��o���Ȃ�Ƃ�����
�y���V�������n�����艿�i900~1200�~�̂Ƃ���
������R���Y�Ƃ��Ă����Ă��A������̂͊����ł��傤
��̂�2�����(����)�ŁA
�M�c�Ȃ�i�_��L64���낤���ǁA�_�˂��c
�L64�͈ӊO��ӊO�A���������̃g���u���͂���ܖ��������炵����
���R�ɂ��������\�z���������͎̂����@�C�R�͂ǂ����낤�@���{���R����@����
>>68 �i�_�͕���V12�ʼnЂ͕s��������
�L64���Ђŋً}�������Ă��߉ނȂ�ł́H
�b�͕ς�邪�O�H��H24�Ƃ��푈���̂���ʎ����Ɏ�Ԃ������ăA�z�Ȏq�H
�n50�A����22�C�����O����n�߂��
�x�ԍ��鍑�͂�����ΑΕĐ�Ȃ��K�v�͂Ȃ������A���
>>69 ���_�A��������(�\������)����d���]�v���y���̗p����
>>68 �ΐ����������ɂ͖��Ȃ��āA�v���y����G���W���̐v�ɖ�肪�������킯������
>>71 ���{�ɕx�Ԃ�����قǂ̍��͂�����Ȃ�
������A�W�A�ɔe��������卑�ɂȂ邾�낤����
�t�B���s���͂��߂Ƃ����������m�̔e�����|����
�A�����J�Ɛ푈����H�ڂɂȂ�������
���d�����Đ������Ɨ�������Ă�
>�͔b��ŗ��21�^�ɏ��Ă����
�ł����̐}�̂ŗ��32�^���݂̔��͐��\
����̃G���W���͍����\����
>>79 1000�n�͂��\�Ȃ���2000�n�͂��\����
�Ȃ�Ȃ�d���m�͂�15���n�͂����ďo���Ă�
����͍̂���]���u�[�X�g
>>77 ���d�����x���̐��\����Ζ����Ȃ�قڒN�����Ă������Ȃ��ȁB
�Ƃ������C�R�n���Ȃ�˂����ƁB
�x�A�L���b�g��P-51H�A�X�p�C�g�t����MB5�ɂ����Ă܂���?
�u�N�����Ă������Ȃ��v�Ə����Ă��邩��}����̂��Ƃ��낤
���Ă�ł���
>>81 1943�N8����204��ꍆ���͗v���Ƃ܂Ō����Ă�̂�
�T�C�p����21�^�ɏ������肪���āA52�^�̃x�e�������U���Ȃ������Ƃ���闝�R�͊���l�����邯��
���͂��̊Ԃ�F6F�̃f�r���[������̂�ˁB
F6F�̐��\�͗��ɔ���A����F6F�Ƃ̊i���ɉ����āA
21�^����52�^�̊Ԃł������A�͂��Ȑ��\�̒ቺ���傫�������\���͖����ł��Ȃ��B
�ƂȂ��21�^�ɂ��珟�Ă�̐��\�͑�F6F���ƈӖ�������̂ł͂Ȃ��낤���E�E�E
>>85 ��킪�������ȏ��F6F��F4F��肾���ԗ����Ă邩��A�����͖��ł͖����Ǝv����
����21�^���A���Ă��ăx�e��������ł��Ă̂��A��l�������߂��������ʼn����̓��v�Ƃ��Ă���ᖳ����(���������_�ŋ@�ނɌ��������߂�Ȃ�T���v��(���s��)�𑝂₷�ȊO�Ȃ�)
���ۂ̐�ʂ�21���ゾ�����Ƃ��Ă�
>>87 ��������Ȃ��Ă��A�����������̗�������Ă���
���ۂ�����̐�ʂŏ����Ă�����͉^
32�^���D���������Ƃ����H�؏��Y�����
�����@���Y���l�������p�@�̑��������@�ύX�Ɋւ���ō�����
���d���C�}�C�`�ŋǐ�~������������ł���
�L100���������D�]�������݂�����
�͑��x��ɊW�Ȃ��AF6F���^�����ɗ��
>>93 FM-2�̕���F6F�����[���Ƃ���Œᑬ�Ȃ炻��FM-2�Ɣ��������炢�ƕČR�ɕ]������Ă���̂ŁA���x�͑傢�ɊW�����
>>54 �@
>1944�N�O���@�T�C�p���ł̐퓬��52�^�̃x�e���������ɁA21�^�̎��B������ƌ����،�����
>>85 �@
>>86 21�^�̎�肪52�^�̃x�e������芈��̘b��
�}���A�i�펞�̗������ł̋������铋����̕�������ɏ������b�Ȃ���
���̓��e���m�肷�鎑���◠�t����悤�Ȕ��������ꂽ���͖���
�œ����̕����j���������l�����ĎQ������������̕��̌o���Ńx�e������������
�������Ƃ���قړ������炢�̍������A�җ��i��A�̋��ő呹�Q���Ă�j
���Ǝ�蓋����̕��͕ґ���3�A4�ԋ@�ŃL�����A���Ƃ�
52�^21�^�ɕ������ƂȂ��52�^��21�^�̍�����������ɂȂ�̂�
���̂悤�ȕҐ��ɂ��鎖�͍l���ɂ���
�Ō�͏،����ꂽ���̉����̊��Ⴂ�ł͂Ȃ����H�Ƃ������_�ɂȂ��Ă���
>>93 �A���_�[�p���[�Ȃ��߂ɐ���ňʒu�����x�������Ď������Č��Ă���邾���Ȃ̂ł́H
>>89 �H���������ČR�̐i�����ɖ؍X�Âŗ���Ԃ��Ă��ă{�[�g���V���ɂ��ď㗤���邩�Ƒ҂��\���Ă�����
�����Ȃ荻�l�ŊC�ɍ~��č��܂ŊC�ɐZ����Ȃ���G�O�㗤�݂����ɂ��Ă�
�A
��������Ă��H����́A�푈���I������̂ɂ���J����A�Ǝv���Ȃ���
���C���Ă����Ă܂��g�̂����߂ĉ�����
�Ɛ��g�����Ή����ĂȂ��������H
�{�y�h���Œ��ԂƂ͂��ꂽ����1�@�Ɨ��2�@�ŕґ��g�b�͂�������
���̍��������]���\�������̂̓G���������ᑬ���̐v�ŁA
�ő呬�x�ɋߕt���قǗ]��n�͂͏������Ȃ邩��A���x���グ�Ă����ő呬�x���x�������s���ɂȂ�͓̂�����O
����ς����Ȃ�
���������ꌩ��ɂ��v�����A
����������ƃG�������������ɂ��Ă��ǂ��̂ɂ�
���ɒᑬ���ǂ����߂����A
Fw190�ƌ݊p�Ƃ����C������( ;�L��֥`)
>>102 ����͖{���ł͂Ȃ��ău���O�̒��L�c
�{���͌������Ƃ��邯�ǁA�E�B���O�X�p��12m��21�^�Ǝv���邵�����ɂ͂�����50�|���h���ď����Ă�������
>>103 naca���|868�̃O���t�ɂ͐Ԑ��������Ȃ���ΐ�����
�p�R�e�X�g��32�^�f�[�^��brog�傪�����������̂��Ԑ�(�����])�Ɛ�(�E���])
101�̃O���t�͉��H����Ă邩��brog���{���ō����Ă�
>>104 ���̘b�H
���͖{���ɂ��Ęb���Ă���ǁB
No.868�͓ǂ�ˁH
�O���t����Ȃ��Ă����ς��^���^�������Ă����āA���̒��ɗ��̏���(��������21�^�ƕ�����)��50�|���h�Ōv�����Ė��L����Ă��
�O���t���ǂ��������ĉ��̂�������
�Ƃ��������������A�{���Ƃ͉����������Ă��ˁH
>>105 101�̃O���t�\�����̂͌N�ł͂Ȃ��́H
�ŏ����猴�T�̃O���t��\�낤
��Fw190�ƌ݊p�Ƃ����C������( ;�L��֥`)
����͈�̉��Ɣ�r�����H
���|868�ɂ͂Ȃ��Ԑ�����Ȃ��Ƃ����牽�������Ă���
>>107 ���̂��߂̃��b�`���C����c�ʐl�ł����H
�ŁA����ɓ����Ă���Ȃ��݂����Ȃ��ǁA�{�����Ȃ��Ɩ��C�Ȃ��Ƃ����Ȃ���\�������̂́A�{���ł����ł��Ȃ��̂����ǁB
�������� NACA No.868��2016�N����ɓǂ��ǁA�Ƃ����Ƀ����N�ꂵ�Ă邩�獡�͊m�F�ł��Ȃ��������ǁB
�{���ɌN�͖{�����m�F�����̂����H
�u���O�̐l�����炩�ɖ{���Ƃ͖������鎖�������Ă����B
���͐풹�ňȑO�ɂ��u���̃O���t�̂͑���͂��s���Ƃ��邩��K���ł͂Ȃ��v�Ǝ咣�����������āA����ɑ��� NACA No.868�Ɂu�{���̕���50�|���h�Ɩ��L����܂���v�A�Ƃ���������肪��������B
���炩�Ƀu���O�̋L�q���Ԉ���Ă��āA�����s�K���Ȃ��̂�{���ȂǂƏ̂��ē\��̂͂ǂ����ˁH�A�Ǝv���ċꌾ��悵������
���`�A�S�������������S����
>>110 �X�}�����Ԍo���ĂċL�������ꂽ�̂Ɖ��̏����������������ȁA�u���T�v���[�̂�TAIC�̃��|�[�g�ł����� NACA No.868���[�̂͂��̃O���t����l�������������Ō�����ꂪ���������̔�r���|�[�g�Ȃ�Ă��̂���Ȃ��ĕ⏕���̑��쐫�ɂ��Ă̘_���B�ŁA���̃��[�����[�g���������Ȃ�@TAIC�ł�stick force��50�|���h�œ��ꂵ�Ă����Ď��B�����猴�T���ł͖����͂��Ă��Ȃ�
>>111 �Ƃ������Ƃ͂܂�
�����ǂ߂Ȃ�����taic���|�[�g��naca���|868��zero�Ȑ��Ɠ��ꂾ�������Ď��H
�A�N�^���[���̃t���C�g�e�X�g
200�m�b�g�ŃG���������d���Ȃ�
���O���t����ǂݎ��Ȃ��͓̂䂾��
http://www.wwiiaircraftperformance.org/japan/ENG-47-1673-A.pdf �������ł�300�}�C��������
>>112 �y�[�W������50�|���h���������
Wikipedia�̉p��ŃA�N�^���[�������Ă��炦��Ηǂ����ǁA���͂����܂�200�m�b�g�ŃG���������R�`�R�`�Ƃ��������ĂȂ��̂ŁA�O���t�݂����Ɍ��X�ǂ��Ȃ��������[�����ǂ�ǂ��Ă��������Ƃ����̂͂Ȃ�炨�������Ȃ��B
50�|���h�ł̃f�[�^���ƁB
���������ATAIC��50�|���h�Ƃ����̂�����Ȃ�ɍ������鐔��(��ʓI�ȃp�C���b�g���Ў�ŏo������p�I�ȑ���͂̌��E)�œ��ꂵ�đ����Ă��邱�Ƃ���A��킾��30�|���h�͗L�蓾�Ȃ����ƁB�����͋@�̂̃|�e���V������������̂����猈���ē��{�R�ۛ��ڂɌ��Ă��Ȃ���(���Ⴂ����邯�ǁA�L���ȏ����ő�����s���̂͊���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��đ����̐��\���オ�����Ă��Ή��o����悤�Ɍ��z���Ă���ʂ�����)
>>113 ��50�|���h
naca���|868�̃O���t�̉��̋L�q�H
�e�@��50�|���h�ɓ��ꂵ�����zero������force limits unknown�ł����Ď����S�Ă��Ȃ�
unknown�����牽�|���h�Ƃ���肶��Ȃ��̂����m���
�r�͂���C�͂ɏ������͉E�オ��A�t�]����ΉE������
�R�����n�b�L���o�Ȃ��͍̂����ቺ�����̂����Ƃ����\�������邯�ljp�R���e�X�g����32�^�͎R�����n�b�L���o�Ă邩��Ȃ�
�����ቺ�����̓G���x�[�^�[�̂�
���{�R�̒E1000�n�͋��V�s�@���C�R�@�����R�@��
>>117 �܂������^�����̒i�K�œ��{�̋Z�p�͓I�ɂ͂��Ȃ�w�L�т��Ă邵�A
���̏�ŗ_�͏��a���̂��߂ɂ��Ȃ�̖��������Ă�B
�h2x�����5x��18�C�����ŁA�ߓx�̏��a�������߂Ȃ����
�n42�̗���l���Ă����������肵���G���W���͍��Ă������ˁB
�A���A�h2x��18�C���������G���W���͋���5x�Ƒ卷�Ȃ���
����5x��18�C���������G���W���͉ΐ�1x�ɂ͏��邪�ΐ�2x�ɂ͗��B
����ȃG���W���́A��풆���ȍ~�̕Đ퓬�@�ɑR����ɂ͖�s���B
�u�͕s���v�Ɓu��s���v�͑S���t�̈Ӗ��Ȃ̂Ŏg���ԈႦ�Ȃ��悤�ɋC�����悤
��ˍD�Â��Љ�����O�^�ƌ�킵��P-47�̃p�C���b�g�̒k�ŁA�u��X���㏸��2�������A����͔{�����v�Ƌ��ЂɊ����Ă�����
�P���Ȑ����E���Y�����l������@��͏W�������ǂ�����
>>120 �����������̂��h�C�c���ȒP���퓬�@���ق�Bf109��Fw190�ɏW���Ă�
Fw190�������g��Ȃ����łł��邾�����Ղ����Ă��̂ō̗p���ꂽ������
Bf109�����ɏW��Ă��\�����炠�����B
�܂����ʂ͍ő����Y�@�����L�^���������ȏ�̓G�ƃp�C���b�g�A�R���s���Ŕs�ꂽ�킯����
���Y���Ő�ǂ̑��������������킯�ł͂Ȃ��͕̂]�����Ă����B
���ƃ��o�E���q����̕�
�Â�21�^�Ȃ���Ȃ����点�߂�52�����V�^�퓬�@�i���d�j��z���B
�Ƃ����̂��L�������A
�����琔�𑵂����Ƃ���ł��ꂪ���|�I�łȂ�����A���\���Ŕs��ăW���n�ɂȂ邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B
���ꂱ���p�C���b�g�̗{���͐퓬�@�̐��Y�����R�X�g�������邩��B
>>121 �Ȃ����ČR�������̗��R�ɋ�킵�āA��킾���̊C�R�ł̓_���݂����Ȃ��Ə����Ă邯��
����Ȏ����͂܂������Ȃ���B
���S�ɃL�~�̃~�X���[�h�B
���������A�����J�͓��{���C�R�o���Ɠ����ɐ���Ă�����瓖����O���Ƃ킩�肻���Ȃ��̂����B
>>123 ����Ȏ��͌����ĂȂ���
�P�ɕ����̋@��������Ďg��������
�G�ɕ��S�������鎖���o������Ă���
�ČR�͕�����Ă����{�l�̍�������ɋ�������ē��{�@�̎��W�ƕ��͂ɕK���ɂȂ�������
>>124 �����炻�̕����̋@���������Ε��S�������邱�Ƃ��ł�����Ă����̂�
�����̂Ȃ��L�~�̃~�X���[�h�Ȃ̂�
�Í����������Ă�����Ȃ��Ƃ��ċ�����ĂȂ��ł���H
���{�@�̏ꍇ�A�ČR�ɂƂ��Ă͎����̕��������ďd������Ώ��@�قڂ������傾����
P-39��P-40��F4F���A�J�^���O�X�y�b�N�ƈ���ė����x���A�}�~���ȊO�ł͒ǂ����ꗎ�Ƃ����
>>126 ���ċt�̗Ⴞ��F4F���Ǝv���Ēނ�グ�����肪
F6F�œ�����Ȃ������Ƃ�
F4F�Ǝv���Đ�����FM-2��(����͕ăp�C���b�g�̐�������)
�Ƃ����邼�H
���Ǝ����⎇�d���A���d��F6F���D���Ƃ���邩��
���̕ӂ����ƊԈႦ�Ă���v���I�ɂȂ�댯���͂����ȁB
���B�ł�P-39����Ƀw�b�h�I�������
��(�Ƃ������[��)���Ǝv���ċ}�~���������A���c�������̂ŐU��ꂸ�ǂ��ꂽ���Ⴊ�����
>>128 �����ŏ����Ă�Ƃ���A�댯�������邾���Ŏ��ۂɊ댯�ł��邱�ƂƂ͕ʕ�
������������͏�ʌ݊��Ƃ��Ă̐V�^�@���o�Ă����P�[�X�ł����ĒP�Ȃ�ʋ@��]�X�ł͂Ȃ�����ȁB
�V�^�@���o�Ă��đR������Ƃ����Ȃ牢�B��Fw190�o�ꎞ�������B
�����Ă���͓��{�@����ł͓�����Ȃ�
���d���������҂��D���ƃ��|�[�g���Ă��Ă����ǑΏ��@�͕ς���Ă��Ȃ�����������킩���ȁB
���R�@���肾�ƁA�Ώ����@�u�}�~���ŐU���v�����������ɂȂ�����ł���
���̑Ώ����͋}�~���ŐU��ꂶ��Ȃ��ċ}�~���ő��x���҂��Ńu���C�N��
�Ώ��@���[���߂�ǂ���������������Ăނ���V�^�@�̕����킢�Ղ����肾������ˁH
�A�����A���d�A���d�͏����r�~���[�ȕ]���ɂȂ�������Ă邯��
ki-61���g�����Ȃ���p�C���b�g�Ȃ琔�ň��|���Ă�F6F��|�M���Đ��҂ł��鐫�\�Ȃ��ǂ�
>>131 �����A�����J�͎��d�����e�X�g�o���Ȃ���������]�O�̑�ɑ��邵���Ȃ�����B
�Η��̗v�̂�(���d���̓��ӂ�)�E����ŗ��E���悤���ĉ����ł����̂͋������낤���B
>>138 ���̏]�O�̑�ŏ\���������͓̂��ė��R�̑��Q��r�ŏؖ�����Ă�킯�ł�
���������̐�L�A�u����̉́v���ǂ��NJm���ɒ��҂̈��@���́A��e�㔒�������Ȃ��琂���~���œ�����p�R�@�����x�������Ă�̂����ǁA�t�ɒZ���ˌ��`�����X�ł�������d���߂���Η͂�������ΕK�������G�@���Ƃ��Ƃ�ǂ��l�߂�K�v�͂Ȃ��B
>>139 ���������ˁA�ł������ɍX�ɗ����p������Ă���
�����̈قȂ�퓬�@�ɂ���ăA�����J�̔�Q�͍X�ɑ��������낤
�\�������Ŏ����I�ɓ�����C�R�퓬�@����킵���Ȃ��������Ƃ�
�ԈႢ�Ȃ����{�̎�_�̈�ɂȂ�����
>>142 ���̗������F8F�����퓊���������ǂ˂�
��������x�̐����ʎY����ĕ����z���A�P���I�����Ă悤�₭�������ꂽ����ɂ�
���肷��W�F�b�g�@���肾�悗
>>143 ���Ȃ݂�8��14���ɖL�㐅���ŗ��R�̎�����
��P�ɐ��������ɂ��ւ�炸P-38�ɕ����Ă�
8��15���ɂ̓V�[�t�@�C�A�ɗ�킪�����Ă��
��������8��15���ɂ͌��̗��d�Ɨ�킪F6F�ƈ��������Ă�
���d�Ɨ��͊ԈႢ�Ȃ�F6F�ɗ�邵���d���ɂ���邪
����������đ��荞�ނƓG�ɋ@��̍i�荞�݂Ƒ����点�ɂ����Ȃ�
(F6F���͎����E���܂ޕ����Ƌ�킵���Ə،����Ă���)
�i�㑊��ɏ����Ƃ��\�ɂȂ�̂��B
343��̎��s�́A���d�Ǝ��d�����W�߉߂��ė��̕��p��ӂ����������ˁB
�t��F6F��F4U��FM-2�p�����ĊC�R�͎��Ɍ�����
>>142 ��킵���Ȃ������������Ń��o�E���ɂ��ꂾ���܂Ƃ܂������𓊓��ł����Ƃ�������
���d���炢�͗~������������������p���Ɏ�Ԏ�肷����
>>144 �����t��ɂ�����
���������ő��̗v�������ׂĖ��������Ƃ���Ő����̓[��
�����������̑O�ɂ��̗��d�Ɨ�킪�o�����ė��d�����Ƃ��ꂽ����
�ΐ퓬�@�퓬�ɂ͕s����������������ꂽ��
>>147 �ނ��������ǂ݂œǂ{��
�^�C�g�������O��������ĂČ�����Ă����
���a20�N�t���炢�ɁA�ӊO�Ɨ��d���ΐ퓬�@�Ŏg���邱�Ƃ����������̂�
�ȍ~�A���d���ϋɓI�ɑΐ퓬�@��ɋ��o����邱�ƂƂȂ���
�E�E�E�݂����ɏ����Ă�̂�ǂ��Ƃ���̂�ˁB
�����Ƃ��Č����͏�@����ɗ��d�o���Ă邵
>>143 �����ĕđ����@�����F�������ƂɐG��Ă��邪������ԈႢ�B
���{�����P��@��̂Ƃ��ł��đ��͕��ʂɕ����̋@�����邱�Ƃ��U���ɂ��邩�炾�B
����Ɍ��ԈႦ�邱�Ƃ��s�v�c�ł͂Ȃ����x���łȁB
�O�̃��X�ł��₽��Ɛ퓬���̓G�@�픻�ʂ����m�������ƌ�����Ă��˃L�~
>>149 ��������
�����炱�������̋@��������̂��厖�Ȃ̂�
��@�킵�������ĂȂ���A����������F���̂����������Ȃ������
���A���b�T�[�������Ƃ������g���`�L�͗��ɕʂ�w
>>148 �ΐ퓬�@�퓬�Ɏg����̂ł͂Ȃ��A
���Ԃ�3�����{����n�܂鉫�ꌈ��A�V�ꍆ����302��̗������������̊}�m���ɐi�o����������
���d�𒋊Ԃ̑ΐ퓬�@�ɂ��o������Ȃ����������B
��s�h���302�����Ȃǖ��̑�2��s���͂Ƃ������A�o�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B
���̏؍��Ƃ���
B-29�ɂ���B�������n�܂���4�����{�ɂ͖h���C��302��2���̏W�����d���������ɔh������đΔ����@�퓬�ɏA���Ă���B
���Ȃ݂ɂ���20�N�t��4��19���ɗL����15FG/78FS�����W�F�[���YB.�^�b�v������15FG/45FS�̃h�i���hE.�X�^�b�c�}�����т��ꂼ���P-51�Ɍ������
���サ�Ȃ���ė����Ă������d�̎ʐ^���K���J�����ɑ������Ă���B
���̑O�Ɍ�킵��12���ɂ����d��P-51�ƌ�킵�Č��Ă���Ă���B
���_�A���d�ɂ�錂�ĕ͂Ȃ��B
>>151 P-51�ɂ͓�P������I�ɕ������肷�邭�炢������
�����悤�ȗ��d�ɂ͕��������낤��
>>144 >343��̎��s�́A���d�Ǝ��d�����W�߉߂��ė��̕��p��ӂ����������ˁB
������ԈႢ���˂��B
�ċ@�������̖{�y��P�͍L�͈͂ɋy�Ԃ��炽�Ƃ���
343��̏��w�̋��ł͎��d�������łȂ��A���◤�R�@�Ƃ̌����ċ@�������͋L�^���Ă���B
���R�A����Ő�ʂ��オ�����؋��ȂǂȂ��킯�����B
>>153 �܂��������ď����Ă�Ƃ͎v����
���R����؋�����݂����Ȉً@��ł̘A�g��
���Ȃ��������̎w�E������
���̒Nj��͓I�O��
�ł̎��ʓ�x���l����Η����͍����Ă邯�nj����͈���Ă�ނ̐������
�܂����d���R�P���̂��S����������
�ŁA�쐼������I�Ɏv�����Ďn�߂����ʂ��A������ɉΗ͈ȊO�J�߂�ꂽ�Ƃ��낪�Ȃ����d�ł���
��V��т��l������ꎮ��O�^�̕����D�݂܂������Č����Ă邵�B
�����퓬�c����ʂ����߂��Ⴉ�B
�k�d���������Ƒ������
�k�d�͔�Ԃ��Ƃ����܂܂Ȃ�Ȃ����s�삼�B
>>158 �L46�V���L43�V�����Y�J�n�����̂�1944�N���㔼����E�E�E
�J�둼�@��(�L83�H)�̂����Œx�ꂽ�L46�V�ƁA
�����������L43�V���r���čl�����
����6x�̂��h3x�����������퓊���ł��Ă��\����������B
��풆�ՂɎg������r�I���͂ȃG���W����
�ΐ�1x�A�ΐ�2x�A����5x�A�M�c2x�A�n40�A�n42�A�n109�܂�
���d�̐U����蒼���Ă���k�d�̃g���N���䒼���Ă�����ȒP����
�k�d�͂��̌`��ŋ��G���W���A��������������p�t�@��������悤�����A�C���e�[�N�̑傫�����炵�ĉߔM��肨�����Ǝv��
�ꎮ��3�^���ĉ�z�ǂނƏd�탌�x���̖������������Ƃ��J�߂��Ă�����
�J�����̃T�C�Y����Ȃ��ċ@�̂Ŕ������鋫�E�w�����邩��_�����ƌ����Ă�
���`�̒������ɒu�����@�̂̓s�A�c�W��P.119��XP-56�����邯��
�ߔM�����ɂȂ�̂͗����Ə��q�����琅���^�g�p�ƌ}����p�Ȃ畽�C���낤
>>167 ��������o�̓G���W���łȁB�m���ɉ��M���͑����������肵�����y�����n�ʂЂ��ς����Ă�����R�ς�����B
���ƁA�u��ԏ�肽���Ȃ��V�^�@�v�F�肳���Ƃ����A�k�d���������������̕s�M��
�G���W�������ɂ���ƌ����_�ɕs�M�����������ƌ����b�����邩��
����ł��@�e�O����ki-61�ő̓����肷������}�V�Ȃ�ēz�͋��Ȃ�����
�C�̌������ɂ�R2600���ڂ��������������
���O��s�������鎞�|���Ƃ��E�o���鎞�|���Ƃ��G���W���n�����邾���ŋ��낵��
>>173 ���C�g R-2600����Ȃ��āAP&W R-1830�c�C�����X�v�ł́H
>>175 ����AR2600����A
B-25�Ɠ����G���W�����ď�����Ă�����B
�Ƃ�ł��Ȃ��㏸�͂��ƕ�������
���ɋ@���������|�����Ă邻����
��������͔��̕����@�ɍڂ�����A�d���Ē������ɋr�����Ƃ����b�͉����ŌĂ�
���V�A���[���̎��Ȃ�L���ŃG���W����R-1830�ƏЉ��Ă��
�A�����J��Google�Œ��ׂ����o�Ă����
�ꉞ�����������ׂĂ����V�A���[���̃G���W����R-1830�ŊԈႢ�Ȃ���
>>152 ������������
����P-51�ɑP�킵�Ă���̂�
P-40�ɂ͋�킵�Ă�Ƃ�
�}���킩�����@��q�̐퓬���̈Ⴂ��
���邾�낤��
�����̋@��ň�̐퓬��D�ʂɐi�߂��Ƃ�����
�͔����̎�L��ǂނ�
���V�A���̃t���C�g�V��������P-39���ċ�����ˁH�ƍ��o����̂͊ԈႢ�Ȃ�
���ہA��������ł�Bf109G��Fw190A�ɕ����ĂȂ����AJu87D���炷�����
���{�@����̏�Ƃ���i�̌����������ăo���o�����ƍŋ��i����Ȃ�������
���{�@����ɂǂ����Ă�������Ȃ����_�ŔߎS�Ȑ킢����������͎̂d���Ȃ�
�p�ČR�͚���킪�D������
>>181 P40���Ă�����G�@�ɑ��Ă������яo����ȁB
�\�l���ǒn�퓬�@���Ċ����_�ŊJ�����ꂽ��������
�C�R�̋ǒn�퓬�@�̔C���͊C�R��n�̖h�q��������������h��ɂ����g���Ȃ����\�œ�����O
�C�R��3�N��������o�����Ȃ�����\�͂Ƃ��q���̎��ۂ�����
>>191 �����������퓬�@�̒��ł͎�͂Ɉʒu�t���āA���̉��ǂ�Y�ɗD�悳���Ă��܂��Ă���
�܂������a17�N���ɂ��Ȃ��āA�U���@��o���퓬�@�ōq�Ő��������肾�����̂�
����ɑS�͂�0.7���Ԃ�����ׂȂ��A�\�l���ǐ�̌v��Ƃ����̂��ǒn�h��ɂ��g���Ȃ��Ƃ݂Ȃ����ׂ�
������� Sdfa-DOyQ
>>186 ���{�R�@���R����������P-51�p�C���b�g���A�����l�̕������]�݂��͌��������Ȃ������B
��킪�ُ���Č�������F4F��F6F��F4U���[��������Ԃ�
>>195 �����1939〜1940�N����̉��B����ł̘b
�C�R�͗��𓊓����Ă�킯������A���������@�̂�G���������Ă��邱�Ƃ�z�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�
�S�c�[�ɂ킽��A�L�͂Ȑ퓬�@���q�Ő�́A�o���@�̎��s�œڍ��������I�ƈႢ
���Ăł͌����ɋN���肤�邱��
�݂��ɋ��������Ă邩��A���{���������݂����Ȃ̂��J���ł����Ɠs���悭�l���Ă�
��͂�\�l���ǐ�̌v��͓����̗��s������o�����D�悵���O�����Ԃ�Ǝv����
���[�_�[�O��œG������20���O�Ƃ��ɕ�����Ȃ�g�C���Ԃƌ}�����x��������
�C�R���g����������������ė��Ƃ����̂͐���
�����@�����ł������芸������яオ���Č}�����Ă����A
���d�͂��Ԃ̌`��퐫�\�̈����ɍv�����Ă��ȁB
Bf109��Fw190�ł�F6F�ɂ͕����Ă�̂��A����͌����ڂ��^�������ǂ�
�ނ���P-51�ł����h�C�c�@����Ȃ�ăp�C���b�g���i�������ł��郌�x��
>>185 ��Ƀ\��������j���[�M�j�A��P-39�ƌ�킵������Ƒo���̑��Q�x�[�X�Ŕ�ׂ��
��킪���|���Ă��邩�����I�Ɏ���܂������Ƃ����Ă���
�x�z�Ȃ�ΐ�1x�ŃL100�����̋@�͍̂�ꂽ�͂�
�a���̂ōő�f�ʐψʒu��40%������ɂ���ɂ��Ă�
�ǂ�ȂɂȂ��炩�Ɍq���ł���͂͌������Ă͂���Ȃ�����ǂ�����H
>>203 ���{�@�ƈ���č�����ł̉^��������������
�Ɛ퓬�@�Ƃ��Γ��ȏ�ɐ킦��
�}�E�U�[20�o���������܂�Ă���n�ɋA���ł���
�@�̂̌��S�����G��A�O���}���S�H���̍ō�����
>>204 >�ނ���P-51�ł����h�C�c�@����Ȃ�ăp�C���b�g���i�������ł��郌�x��
��������{�́A�����Ƃ����푈����悩�����B�}���A�i�����������đ嗤�Œʍ�킾���ɂ��ׂ��������B
��������Εč��̂ق����h�C�c�œ|�D��ŁA�����Ƒ�������m���}���f�B�㗤����ꂽ�͂����B
�嗤�Œʍ��̔w�i�Ƃ��čł��d�v�Ȃ̂́A�ĉp�����u�h�C�c�œ|�D��v���������ƁB
�ČR��͂��ΓƐ�Ɍ����������ƂŁA���{�͑嗤�Œʍ��𐋍s���邱�Ƃ��ł����B
�h�C�c�Ƃ̓����͑吳���������A���肪�Ƃ��h�C�c�B
�嗤�Œʍ��̋P�������叟���̗��ɂ́A�h�C�c�̔߂����]�������������Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��B
�@�̂��Ԃ��Ƃ��Ɖ^�����\�����Ȃ���Ęb�͕������ȁB
F4F��F6F�͗��قNjɒ[����Ȃ������ő��x���オ��Ƃ���ς葀�ǐ���������
>>212 ���ƕ⏕�����ł�������ƍ�����ʼn^����������ȁB
�Ƃ��������ʉd�����B
�e�U�e���o�|�T�P�̑���ɂa�|�P�V�̌�q��
�h�C�c�R�@���i���ア�ƌ�����̂́A1943�N�ȍ~�A����������]�V�Ȃ����ꂽ�̂����
���K�����m�ۂł��邩�ǂ������Ⴂ����
�ꉞ�h�C�c��i�삷��ƁAFw190��Bf109������5���@������Ă邩��
�r�����^�̑���ɔR���˂��ďo�͏グ�Ă��肷�邩��
Bf109�ŗL���Ɋi���ł���Ȃ�ă}���Z�C�����炢����
>>218 �����čŖ����ł����퓬�@�����������߂��ė]�肠�鐔���ڂ�ڂ��[���Ă�����̍��B
�p�C���b�g������Ȃ����ǁB
���Ⴂ���Ă�l�������b�Ȃ����{�͊J��ȗ��̉ғ��@�͏I��܂ő��������Ă�
>>211 ���̓y��Z�t�̘b���Ɠ��̕����������Ǝ����A�X�y�N�g���䂪�オ��̂�
�U����R�ŗL���ɂȂ�
�Ƃ������������̂ʼn����̂���ꂽ�C�����嗃�Ƌ�������R����̂��낤
�헪���������c�̃��|�[�g�@Twitter���
ID:5s8uMfmMd�̓��X�݂�Έ�ڗđR����
>>224 ��ˎ��̍q���j��
�m���}���f�B�ȍ~�̃h�C�c�p�C���b�g���Ɛ�ʂɊւ���
�u��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���A���R�@�Ɍ��Ă�������ŏ����̃x�e��������ʂ��グ�Ă������߂ɑP��ł����v�Ə����Ă���B
���ł͖��n�Ȃ��̂������Ă����Ƃ����������̂���
>>219 C-3 injection�Ō�������
�ˌ��͌o���Ɗ����S�Ăō�����Η͂ȋ@�̂ɏ��Γ��Ă���Ȃ�Ęb����Ȃ���
>>226 ���o�E���̎Ⴂ��˂͗ǂ������ċA�ꂽ��
�Փ˂Ƃ����ē��C�͂�������
�l���@�����Ă��Ă�v�͑o���퓬�@�Ƌ��\�͂�x�O�����ĕ������������P���@
>>226 ��ˍD�Î��ł͂Ȃ��Õ����O��
�����������̋L�q�́u�����Ȃ��G�[�X���w������ґ����������P�팒���̋L�^�͎c����Ă�����̂́ABf109���������͂��̂悤�Ȑ��\�I�ɂ���āAFw190���������ڂ����đ傫�ȑ��Q���o���X���ɂ�����(p.308)�v�ł����āA���̌�̃A���f���k�q���̏͂ŋL�ڂ���Ă���u�O���z�����_�ŕ��ϔ�s����100���ԑO��̃p�C���b�g�������퓬�c���x�����j�ƂȂ�w�����v�̘b�ƊW���Ă�b
�v�͈�R����̃x�e�������[�A�Ƃ��~���I�^���悭�����������肵���ڂ��s���Ȃ����x�̒Ⴂ�l��Z�]�X�b�ł͂Ȃ��āA�ґ����ɂ�����b����B
������20��1�Ƃ������|�I���ŁA�A���R1600�@�A�h�C�c�R1500�@�̔팂�āA�Ƃ����ł�������Ă��鎖���番����ʂ�A���̔s��͂����܂Ńh�C�c�R�����߂������ɑ��ĔߎS�Ȕs�k�������Ƃ����b�ŃL�����V�I����͐��^�����P��ł���Ⴆ��343��ȂȂ�Ȃ����x������
>>230 �_�C�u�̔����ƈꌂ���E�͑S���Ⴄ����w
�ꌂ���E�͓G�@�̉���Ƌt�����ɔ����邩�A���̂܂܍����ŃI�[�o�[�V���[�g����(�j���[�M�j�A��P-38��P-40�������)
���c�̌��ł��o�Ă��邯�ǁA�A���R�́AP-51���D�ʂ���}�~���A���d���͍U�������P-51�͋}�㏸�B�}�~���̃X�s�[�h������Ă���̂ŃO���O������������đS���ǔ��o���Ȃ��B
���Ⴀ�����ǔ��o���Ȃ����瓦�����A�Ɠ��{�������Ⴂ���āu�ꌂ���E�v�Ȃ�Č��t���L�܂����̂�������A���Ԃ͓ڂ������邽�߂̎��̍U�������������
�@�e�̖������͂����܂ō����Ȃ��B�����Ă��킵�Ă������A�U�����͍U�����~�ɂȂ�܂ŌJ��Ԃ��B�d�|�����鑤�͑܂̑l������ꌂ���E�Ƃ͑S�R�Ⴄ�B
Fw190A�͌����ډ^�����悳�����Ȃ̂ɁA�}����Ǝ������ăX�s���Ɋׂ�₷���i�������ł͂Ȃ��A�Y�[�����_�C�u�Ő키�p
>>231 �����ǂ�ł���Ȃ�
>>226 �̘b���ґ���킾�Ƃ킩��͂������B
��s���Ԃ̏��Ȃ��p�C���b�g�������Ă����b�Ɩ��������b�ł��Ȃ��B
�㔼���܂������֑̎��ȕ��͂���
Fw190��1941�N�Ɏ��퓊�����ꂽ���_�ŁA����620�L�����炢�o��
���d���������ɓ������A�������炢�ȑ��x���o�Ă��
�\�A�R���b�l���ăe�X�g�����@�̂ł͂���Ȃɑ��x���o�Ȃ��āA����ł̕]����Bf109�ɗ���Ă���
���{�ɗ���Fw190A��600km/h�����X�������炵����
fw190 �̐^��
�j���[�M�j�A���ʂł͂���̒�]��������P-39�́A�\�A��R�ł̃G�[�X�������j�R���C��S���h�j�R�t�k
�J�^���O�l��CAS��EAS����o����TAS�Ȃ��IAS����o����TAS�Ƃ͌덷���傫���ꍇ������
>>234 �ґ����̘b���������̂Ȃ�ςɁu�u��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���A���R�@�Ɍ��Ă�������ŏ����̃x�e��������ʂ��グ�Ă������߂ɑP��ł����v�v�ȂǂƎ����ɓs���悭���ς����ɏ����Ηǂ������̂ł́B
�����̃x�e������������ʂ��������̂ł͂Ȃ��A���m�ɂ͗D�G�Ȏw�����ɂ���ė�����ꂽ�ґ��Ƃ��Đ�ʂ������Ă����̂ł����āu�u��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���A���R�@�Ɍ��Ă�������ŏ����̃x�e��������ʂ��グ�Ă������߂ɑP��ł����v�Ƃ����Ӗ��ł͒��҂͑S�������Ă��Ȃ�����ȁB
�\�A�Ōv������Ă�̂͐퓬�o�͂ł̐��\�ł����ċً}�o�͂ł̑��x�ł͂Ȃ�
>>242 >���m�ɂ͗D�G�Ȏw�����ɂ���ė�����ꂽ�ґ��Ƃ��Đ�ʂ������Ă����̂ł�����
����q���j�̂ǂ��ɏ����Ă���́H
���ꂱ�����҂́B
>>231 �ɃA���^���������悤�Ȃ��Ƃ��܂����������ĂȂ���
>>239 D�^���O��685�L����������O�̂悤�Ɍ���Ă�������644�L���������Ƃ����̂����̏펯���ȁB
A�^�Ɋւ��Ă͂�����̏C���͍��̂Ƃ���s���Ă͂��Ȃ��̂ŏ����^624�L������ŏI�^��650�L���ŕω��͂Ȃ��B
>>244 ��H�ʂɉ��͋M���݂����Ɂu���҂��������v�ȂǂƏ̂��ď����Ă͂��Ȃ����ǁB
�m���}���f�B�[���̗ݐϑ��Q�ɂ�����P��͕����ɂ���Ă���͂���ǃG�[�X�����������킯����Ȃ������ʂ̃p�C���b�g�B�����Q���������Ǒ����ɘA���R�����Ƃ��Ă�
�ꈬ��̃x�e�������ݐϑ��Q�ɗ^����e���Ȃ�Ĕ��X�������
�m���}���f�B�[�̑��Q
6/8〜8/28�܂ł̐퓬�@���Q
Fw190�`-8/F3�̃v�����ł͍ő呬�x670km/h�Ƃ�����
>>249 ���̉��A�����ɃS�e�S�e�Ɣ��e�˂��ނ��o���ɂ��Ă�����
�N���[���ȏ�ԂƔ�r����30-40km���͍ō����x�͒x���Ȃ��łȂ��́H
���{���R�̑���&���e�˂����ė�����2���t������30km���͒x���Ȃ����݂������
�w�ō����x�x�A�o��̂��x���I
>>240 >�ŏ��̂����A�h�C�c�l�͎������������x���\�ŏ����Ă���ƌł��M���Ă���A
���l�ɉ��������m�͌����������ǁA�o��̂��x���I
�I�b�N�X�͐������f�B�t�F���X���Ɩ��[���o�ɂ���ׂ��A�O���[�g�z�[������Ƃ��Ƃ���B
����ȃI�b�N�X�ɐ����́u�������B�͂��߂���S�͂ł��ׂ��������̂��B���͂₨�����v�ƌ������B
http://pegasusathena.sblo.jp/s/article/182312945.html ��
����ł͐������m�̃t�F�j�b�N�X��P�ɂ����y�Ȃ�w
P-51�̃p�C���b�g�����x���t���C�g��700km/h�Ȃ�Đ�Ώo�Ȃ������ƌ����Ă��
>�������B�͂��߂���S�͂ł��ׂ��������̂��B���͂₨����
�@�����̐l�X���A�ō����x���傫�Ȕ�s�@�ł���ΐ퓬���x���Ɍ��܂ő傫���͂����ƍl���Ă��邪�A
���͂�������Ȃ��B�Q��ނ̐퓬�@���r�����ꍇ�A�Е��͍ő呬�x�ő���𗽉킷�邪�A�퓬���x�ł�
����ɗ���Ă���A�Ƃ����P�[�X���������B�퓬���x�ɖ{���I�ȉe�����y�ڂ��̂��A�G���W���̋}�����͂�
�o�͏d�ʔ�Ƃ������t�@�N�^�[���B�����̗v�f�ɂ��A�ő���̉������\���ۏ����B
https://geolog.mydns.jp/www.geocities.co.jp/SilkRoad/5870/golodnikov3.html >�������B�͂��߂���S�͂ł��ׂ��������̂��B���͂₨����
�K�E�Z�̔������Ԃ���������I
https://dq10.news/17762 �@�̓��̔R�����ڗ�
���d�Ƃ������͂����v��ʂ�̏o�͂���Ȃ�AP-51�Ǝ����I�[�����E���_�[���ȁH
���d�͋����ɉΐ���Z�^���ځA����퓬�@��&�ᗃ���������������̂ł͂Ȃ�����
>>255 �h�͒������O�X�g���[�N�ŏ��s�R������Ԃ�ǂ�
�t�Ƀh�C�c�R�@�̓���DB605��BMW801�̓{�A�����ΓI�Ƀf�J���ď��s�R��͂��Ȃ舫���B
�t�ɑS�͉^�]���̑؋Ԃ́A32�^�ȍ~�̗��Ƃ͋ɒ[�ɂ͈��Ȃ��Ƃ����̂��������Ƃ�����
Fw190�͗����^���N�������悤�ȁH
>>256 �����Ĕėp���������čq���������h�e������A�������ł���2000�n�͋��G���W�����ڂ�F6F��F4U�Ƃ����Ⴊ�����ŁA�����ɏ���������K�v�͖�������
>>259 �����ł͂Ȃ��R�N�s�b�g���A���̕�����͂ݏo���ĂȂ��h�R�^���N�������A�����̃p�l�����O���Ď��o����
���Ɣ����^�ł���G�^�ŁA���E�����ɑ�����ς߂�^�C�v������
>>257 �Ƃ�����14�����O�H�łȂ��쐼�ɂ�点��悩�����B
�ŏ�����ᗃ�Ŏ��d����������낤�B
���d���͂͂邩�ɂ܂��B�O�H���Ɨ��̉��ǂɖv���ł����B
�����������̎��_�ł̐쐼�ɁA����퓬�@�̊J���o����������������A��������Ȃ�Ďv�����킯���Ȃ�
>>265 ��������肪����Ă����悩�������ǂȁB
�ΐ��ςI�[�\�h�b�N�X�ȋ@�̐v�����ĐU�����ł����Ƃ�������Ƃ������ɂ͂Ȃ�Ȃ������ɈႢ�Ȃ�
���ʂɏ��c�̉ΐ����ڔŁi���ŎO�H�̋@�̂ɒ����̃G���W�����������炻�̋t�Łj�ł�����Ă��炦��
>>267 ���R�͊C�R�@�̓����ɒ�R�͂Ȃ������݂��������C�R�͗��R�@�����͂�����Ɓc
�C�R�����R��100���i��肽�肵�Ă邵�w�ɕ��͑ウ���Ȃ��ꍇ������()
�������x�z�Ɏ��d�Ɨ��d�����C���悤
���͔ƌ��O�ŗV�Ԃ̂ɖZ�����Ă���ȉɖ�����
���͎�ki-61��ki-148�ʎY���Ă邭�炢������G���W���ȊO�͂��Ԃ�]�T
�G���W���͋����g�킹�ĖႦ��
���z��L(���b�h�T���E�u���b�N�N���X)�ł̓��P�b�g�e�𓋍ڂ��Ċ͑D�̑�C�ׂ���S���A�������̘I����������Ă���
���d�Ƃ����̂͌���Ɖ����Ⴄ����c�H
�����Ȃ�A���̓n40�Ɏ���o�����O�H�����̉���������Ă�Ηǂ�������
���̃J�b�R����ki-61�����܂�Ȃ���Ηǂ�������
��Z���Ƃ������ɐl�̏W�܂��
���H���h�̔�^�͊m���ɃJ�b�R����
���R�ɕ��D����ėV��ł��l�����������������
�t�@�X�g�o�b�N�͎̔��͂��܂肩�����悭����
�͂Ȃ������Ƃ��Ă�Ƃ��������b�T�[��ČR�t��@�݂������֖҂Ȋ������Ȃ����C�^���A�@��X�s�b�g�݂����ȗD�낳���Ȃ���ȁB
���̋@������ł�ki-61������Ε����邪���b�T���ǂ��납�O���C�_�[�݂����ɃX�}�[�g��
�{���ɂ������肵�Ă�̂́A�L60�̕����Ǝv��
�͑@�ׂȂ����ɑ唼���O�n�̈������ō��g���ꂽ����A�{���̎��͈ȏ�ɒ�]���ɂȂ��Ă�Ƃ͎v��
�@�ׂ��Ă̂̓G���W���ŁA�@�̂͊��Ȃ�H
�O�����ƃG���W�����i�̊����x���̂��P�ɔz�Ǖ��@�Ǝ�舵�����ǂ��Ȃ������Đ���������
>>289 ��������ȕ��d�������Ȃ��Ă������͏��c�ł����ƌy���Ă����݂Ɋ��ɂ���v�����Ă邩��Ȃ��B
ki-44�̎嗃��ki-61���݂̋��x�������Ƃ����b�͌��������������ǔ�r���ꂽ���|�[�g������́H
Wikipedia�ɏ����Ă���R���̂��Ƃ��ᖳ���́H
ki-61�͓������R�Ȃ̂ɋ}�~��������850km/h�Ȃ��ki-44�̎v�z�����������]�X�̋L�q�Ɩ������E�E�E
39�N�@7���@�L48����@����
���ƊC�R���߂���Η��j�͕ς���Ă���
�L119�̌v��ł͍s�����a600�L�����[�g���A�ő�ōs�����a1000�L�����[�g��
>>246 >���ʂ̃p�C���b�g�B�����Q���������Ǒ����ɘA���R�����Ƃ��Ă�
���ꂪ�A���^�̖ϑz����B
�u�����Ɂv�Ƃ����̂��ǂ̒��x�ł��̍������܂����������Ă��Ȃ��B
�������A�����炾���Ă܂��������Ƃ��Ă��Ȃ��݂����ȋɒ[�Șb�͂��Ă��Ȃ����A
�h�C�c�͎w�����ɗD�G�ȃp�C���b�g�ĂĂ邩��K�R�I�Ƀx�e�������G�@�𗎂Ƃ��@������邵�A
��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���O���ɑ����Ă���ȏ�A���Q�����R�����Ȃ�Ƃ��������̘b�������Ă��Ȃ��B
����Ɍ�����Ċ��ݕt���Ă���A�z�ɂ����������
>>299 �A���R�퓬�@�̗ݐϑ��Q��1600�@
�����������ꕔ�̃G�[�X�ɂ����̂Ȃ�ΐ��\�@���Ẵp�C���b�g�����\�l�ƒa�����Ă��鎖�ɂȂ�(���邢�̓X�R�A��L���Ă��鎖�ɂȂ�)
>> �h�C�c�͎w�����ɗD�G�ȃp�C���b�g�ĂĂ邩��K�R�I�Ƀx�e�������G�@�𗎂Ƃ��@������邵�A
��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���O���ɑ����Ă���ȏ�A���Q�����R�����Ȃ�Ƃ��������̘b�������Ă��Ȃ��B
�ŏ����炻�̒��x�̃g�[���Ō�����B
���ۂ͂����炩�x�e�����͐�ʂ����������A�ɓx�Ƀx�e�����̐�ʂɈˑ����Ă���킯�ł͂Ȃ�
���������w����������G�@�𗎂Ƃ��@�������Ƃ����͉̂����K�R�ł�������ΊW����������Ă��Ȃ�
���ǎ����̒������́u�K�R�v�u�����v�Ƃ������t�ł��̂�����Ă���̂��S�Ăł́B
>>300 �����̈���\�[�X���o���Ȃ��B
�܂�A�ϑz�m�肾�ˁB
�N�Y�̑���͂��Ȃ����������
>>300 �A���^�̔]���ł�
>>226 �u�����v���u�����ꕔ�v�ɕϊ������킯���B
�S�R�j���A���X���قȂ���A
�]���ŏ���ɂ�������ĉ�₂��Ă邩�瑼�l�̃��X���܂Ƃ��ɗ����ł��Ȃ�����B���o�ł��Ȃ��̂��H
>>302 �c���̈Ⴂ�ɈӖ��͂���̂��H
�ŏ��Ɏw�E����Ĉȍ~�u���Q�������v�Ƃ�������Ȃ��Ȃ����������������l�ɁA�M���͗ݐϑ��Q�ɐ�߂�命���̃p�C���b�g��1�@1�@�ς����Ƃ������̂��S���l���ĂȂ������ˁB
���ꂾ���̐��̐퓬�@������Ă����Č��Ă���Ă���u�����̃x�e�����̐�ʁv����߂銄�����ǂ����Ă������Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����l�����B
������Ȃ�1500��1600�̑��Q��͑命���̃��[�L�[�p�C���b�g�ɂ����̂��x�z�I����B
�N�̘_�������m�̂������K�͂ȋ��Ō����Ȃ瓖�Ă͂܂邩������Ȃ��B�ł����ꂾ���T���v������ς�ŕ��ω�����Ă���̂Ɍ��Đ�ʂɋɒ[�ȕ肪����Ȃ����͑�햖���̌l�L�^�Ƃ��Ďc���Ă��Ȃ��̂��܂�ł��������B
��ԕ��͐��ɂ��������G�s�\�[�h�Ɍ������Ȃ��킯������ˁB
�N�̘_�@�����Ȃ�A��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���O���ɑ����Ď吨���߂�ȏ�ȏ�A��ʂ����R�x�z�I�Ƃ����u�����v�u�K�R�v�̘b�������Ă��Ȃ��B
��������ɔ�ׂĘA���R�@�̕��ϔ�s���Ԃ������p�ċ@�����
>>303 �Ⴂ�̈Ӗ����킩��Ȃ����x�̗���͂����Ȃ��Ȃ�u������v�Ə��������H
��������킸�A�Ȃ�̏؋����Ȃ��Ɂu���Ⴂ�v�ƃA���^�����Ⴂ���Ă���̂����m�����Ĉ��ꂾ��
����Ƃ�������̈Ӗ����킩��Ȃ��قǂ̃o�J���������E�E�E
>>304 ���{��343��Ȃ��b�ɂȂ�Ȃ���A�ƌ������͉̂������ǁB
�h�C�c��R�̓��[�L�[��̂ł���Ȃ�����{�Ƃ͂��������ʂ��ς������Ƃ��ĕ]�����Ă���킯������h�C�c��R�̗�Ō���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��B
�@�̂̊i�����\����������ɕґ����ł͌㔭�̓��{�Ń��[�L�[��̂̕����łǂ�����������Ă��Ӗ����Ȃ��B
>>305 �Ȃ�قǁA���X�o�ɐ�ւ����킯���ˁB
���̈Ⴂ�ɈӖ��͖�����B���O���}�E���g(�ɂȂ��ĂȂ�����w)�����������̉��l�����Ȃ��B
���{��Ƃ��ď����́u�����ꕔ�v�Ɍ��������Ă����̖����Ȃ��ƌ��������B�g���l�̏���B
���l�̕��͂����p����̂ɜ��ӓI�Ƀj���A���X�̈قȂ錾�t�Ɍ���������̂��u�g���l�̏���v�˂�
�܂�A�A���^�͊w���Ȃ���
�_�������������ƂȂ��������B
>>306 �ŁA�o�J�̓h�C�c�̃��[�L�[���u�����v�ɐ�ʂ�������������o���Ȃ��Łu�o�����͂��v�ϑz���Ă�킯����
���{�ꂪ�ł��Ȃ��o�J������Ɋ��Ⴂ���đQ�������F�߂��A��
>>308 �N�̔]���́u�����v�ȂǂƂ�����ʉ��o���Ȃ����̂��A�����ꕔ�ƌ������Ƃ���ʼn��̈Ⴂ���Ȃ��B
���x�̍����ʉ��o���Ȃ����_�ŗ��҂͓����Ӗ��B
�ŁA�h�C�c�̃��[�L�[�u�B�v�͌l�����c�邱�Ƃ͖�������ˁB�ݐϑ��Q1600�@�Ƃ����̂��S�Ă���B
>>309 �u�[��������
��ʉ��ł��Ȃ��Ɣᔻ�������Ȃ�
�A���^�́u�����v���܂���ʉ�����悗����
�o�J������Ȃ���������
>>309 >�ŁA�h�C�c�̃��[�L�[�u�B�v�͌l�����c�邱�Ƃ͖�������ˁB�ݐϑ��Q1600�@�Ƃ����̂��S�Ă���B
�܂�A���[�L�[�̐�ʂł���؋��͂Ȃ���
�ϑz���Ƃ������ĔF�߂��킯�����A���������낤�Ȃ��̃o�J������
�㗤1���ځ@�h�C�c��R�퓬�@12�����@�A���R17����(����������̂�)
�㗤2����71�@��89�@(��������������̂�)
�T�@
������������Ă��T�˃h�C�c��R��萔�ŏ���A���R�̕������Q���o���Ă���A����̓m���}���f�B�[�q����ʂ��������Q�ł��T�˓�������
���I�s���Ƃ����͔̂��Ƀn���f�Ȃ킯�����A�g�D�Ƃ��ăx�e�����w�����������̃��[�L�[���w������Ƃ�����Ԃ̃h�C�c��R�͘A���R�ɑ��F�Ȃ��ǂ��납�s�x�L���ȏ�ɑ��Q�ȏ�̏o���������Ă����B
����͂ЂƂ��ɍ����d�����̐퓬�@�ƁA�ґ���킾���͍Ō�܂ł܂Ƃ�����������B
���{�R�̗��E���͑��c���̂͊ȒP�Ȃ̂����A���߂�v�f����肾����
>>311 ��킾���ŗݐϑ��Q1600�@���A���R���Ō��Ă���̂����班���̃p�C���b�g�̐�ʂ����ł͐������t���Ȃ��B
�ґ����̉����邩�������������Ă��Ȃ���
��C�ŒĂ������͏��O���������H
�Ƃ肠�������d���X���œ��{�̖��n��������͐�ʂ��������Ȃ�����
�����1600�@�̋�푹���̑������������ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ȃ�č������Ȃ�����͊�{�I�Ɉ�l��l����ʂ����Ă邩�炾����ȁB
>>314 �A�z���Ȃ��B���R�ȏ�̑��Q��^�����Ă��Ȃ����炻�ꂾ����l��l�̃p�C���b�g�̊�����h�C�c�ɗ���Ă��B
��ʑ��c�m����肭��͉��o���Ȃ���A�Z���Ԃ����K�͂ȋ��ł�������u��������v�ɕK���o��B
���܂��������킢����������ł��ǂ���Ȃ����ˁB�ł��ʎZ��т͎�������B
�������䂾�Ƃǂ��Ȃ邩�͕������
�����m�̐킢�͈��V��Ƃ̐킢�ł������������
���[���b�p����P-51�ł����i���킵�Ă邩��o�����͐s����܂Ő���Ăǂ��炩��������
�C�R���ŏ�����2���e�ɒ��͂��Ă���
�P���Ɍ}�����͗L���ŁA�N�U���͂����W���ȂǂɎ��s������
>>266 �퓬�@�����̑�n�͉������ΐ��͂���͂���ŐU���o���Ȃ��H
>>267 ���͒����̃G���W�������炢�����ljΐ����Ƃǂ�����H���c�����̉ΐ��̐��Y��A���Ƃ��H
���₾����A���̎��ɎO�H�����А��̃G���W���ʼn䖝���邱�ƂɂȂ������A���̋t�ł������͉䖝���Ă�����Ęb
>>321 ���d�̐U���͖x�z����͂��l���ăG���W��������ɉ����ăv���y�����������������ɂ���Ďn�܂����̂ʼnΐ��̌��ׂł͂Ȃ��B
���Ƃ����]�����Đ퓬�@���ɑ��荞�܂��Ȃ狭���̐퓬�@���������ȁB
�قƂ�ǐ퓬�炵���퓬�����ĂȂ��B
�������ɔz�����ꂽ��I��܂Ő����Ă�����B
���c�͗���20�~���ڂ���ƁA�@�֕������ł��ł����o���W���ł��đ��x��������
�����E�ҖC�����邭�炢������C�P��
���d�͉������p�~�Ńy����^���@�a���o�b�t�@���[
>>324 �������͐U���Ƃ͖��W
�v���y���������Ⴂ���߂ɉH�����O������ɎP���J���������悤�ȐU��������A���U��
�ΐ�23�^�𓋍ڂ���14���ǐ���̎���@�̏���s�Ŋ����i�Ƃ���1���ǐ�(���d�j�̃v���y��
�����Ď�����s�������͐U���͏o�Ă��Ȃ��B
���d��p�̃y�������Ă���U����������
1�N��Ƀy�����������߂ĉ�������
�i���������������点�����N���X�̗����x��
�P���Ƀv���y���������Ⴂ��Ȃ��ċ��R�v���y���̋N�U�����������̌ŗL�U���Ƌ��U������Ȃ���
���d�Ɏ��d�̃y�������̂܂ܐς߂ΐU�����͋N���Ȃ�����
���d�������Ɏ��p�������Ƃ��āA21�^�̐��\�Ȃ珺�a18�N�̎��_�ŗ�����킵����
�悭���悤�Ƃ�����t�ɖ��N�������ē��̈��������҂݂������B
�O���̂�����{�ɂ��悤�ɂ�1941�N���낾�Ƌ��ő����̂���Fw190���炢�����Ȃ�������
��Z���������x�����@�̐v�{����s���������͂ł���ďؖ����Ă���O�H�A������
>>329 ��III�^�ɂȂ�ƁA�u���x�͗��̊e�^���D���ƂȂ�A�㏸�́A�q�������A���c�����������A����Ă���͕̂����̂݁v�i�哇�v�喱�j�����ǁH
>>336 �����犸���ē��N���X�Ə������B
�������x���̃G���W���ł͔��͏�ɗ��̌�o��q���Ă�B
�@
�܂��A�����������V�^���őQ��52����ɒǂ��t����������
�ʂɔ���������Ȃ����B
���{���̃f�[�^�ŇV�^�b��560km/h(576km/h�͕ČR���ς���)�A52�^��565km/h�B
���ꌜ�ˑ��u����������Ƃǂ��ɂ��Ȃ�����̂��E�E�E
>>337 �܂��������A52����ɒǂ��t�����͇̂V�^�b��
�J�^���O�X�y�b�N�ł͗���Ă��I�N�^������86�Ƃ�����Ȃ̂Ńe�X�g���Ă邩����킯�ŇT�^���C�R��̂��g����512�L���o�Ă��炵�����ǂȁB
�X��I�^���Ɠv���y��������
�������������ł͂Ȃ��A
��������������@�܂ł͌Œ�s�b�`�v���y���E�E�E
>���Ɣ��̂����ꂪ��͖ʂŗD��Ă������ƌ����b�����Ă���
���łɗ��ʐς�`����������Ă�̂ɁA���̌`��̋�͍��Ȃ�ĒP����r�ł���
���d�̖a���`���̂��A���ꂾ������������ƒ�R�����Ȃ����A���@�Ńv���y���㗬������ƁA������t�H�b�P�E���t�݂����ɍi�������̌`��̕����D��Ă��肷�邵
>>344 �������ɍl�@����̂��y�������
R1830���ڂ̃��v���J���m�Ŕ�r�����ꍇ
���V�A22�^�͇V�^�b��葬�x���o��������
���32�^�̊J�����ɗ��[�Z�k(1.14���Ă̗��ʐϏk��)��5�m�b�g���x�̑����������܂�Ă�
22�^���0.44���ė��ʐς����������V�^�b�́A�{���Ȃ炿�����22�^��葬�����炢�̂͂��B
���Ɖ��Ƀh�����^�e�q�̖c��݂��Č�����Ă�Ȃ�A
�X��5�m�b�g���x�͔��������Ȃ��Ƃ��������B
����Ń��V�A���͑S�̓I�ɋ��x�������Ă��đ��x�������Ă�\��������B
��a��R1830�ɍ��킹��Ȃ瓷�̑������̂��L���H
�r�J�o�[�Ȃ����甹�̂��x������i�K��
>>316 B-17�����łW�O�O�O�@�����Ă���̂ɁH
>>345 ������������
�ŋ��̋��V�v���퓬�@��F8F���V�[�t�����[��
�����̎d����Fw190A�Ƃ����ԈႤ
>>348 �퓬�����Ȃ瑾���m�őS����8000�@������
���B�ɉ����y�Ȃ�����
�����m�ɂ͓��{�R�ȏ�̓G������E�E�E
�g���h���Ƃ����
���{�{�y�Ō��Ă����ČR�@�̃W�������~�����čė��p�ł��Ȃ������̂��H
����ł��Ă��債���ʂ���Ȃ�
B-29���������Ƃ����瑊���ʂ̃W�������~����
>>312 >>315�Ɍ�����(��߯� Sdfa-hwij) ID:yRKOZyAMd�̖ϑz
�u�h�C�c�͕ґ����ł����ꕔ�̃G�[�X�p�C���b�g�����łȂ��A���{�ƈႢ�A���n�ȃp�C���b�g�������̐�ʂ��������i���������j�v
���x�l�₵�Ă��{�l�͂��́u�����v�Ƃ�����ʉ��ł��Ȃ��i����F�߂��u�[�����������j���ŌƑ��ɂ��떂��������炵�����A
�m���}���f�B��̐������ԂŘA���R�ɓ����x�̑��Q��^�����Ƃ��������݂̂�
�o���L�x�ȃG�[�X�p�C���b�g�ł͒B���s�\�Ȑ����ƃ������Ɍ��ߕt���Ă������Ă���ɂ����Ȃ�
�ȉ��A�\�[�X�t���ł��̖ϑz��ے肵�悤�B
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_II_aces_from_Germany German day and night fighter pilots claimed roughly 70,000 aerial victories during World War II, over 25,000 British or American and over 45,000 Russian-flown aircraft.
103 German fighter pilots shot down 100 or more enemy aircraft, for a total of approximately 15,400 victories.
Approximately 360 German fighter pilots shot down from 40 to 99 enemy aircraft for a total of approximately 21,000 victories.
Approximately 500 German fighter pilots shot down from 20 to 39 enemy aircraft for a total of approximately 15,000 victories.
These achievements were honored with 453 German day fighter pilots and Zerstorer (destroyer) fighter pilots and 85 German night fighter pilots (including 14 crew members),
�h�C�c��R�p�C���b�g�̎咣������ł̌��Đ�ʂ͂��悻70,000�@�i�p��25,000�A�\�A45,000�j
�����A20�ȏ�����Ă���G�[�X���v51,400�@���咣�A���Ɍ��Đ�ʂ�73.5���ɒB���Ă���B
����������͈�ʓI�ȃG�[�X�i5�@�ȏ�j�̂����A5�`19�@���ẴG�[�X�̐�ʂ��܂�ł��Ȃ��B
�܂߂��80���ȏォ����ȏ�ɒB����ƍl����̂��Ó����낤�B
�h�C�c�R���A���R�@�𗎂Ƃ����Ƃ��A4�@��3�@��5�@��4�@�A���邢�͂���ȏ�̊����ŃG�[�X�����Ă��Ă����Ƃ����������e�Ղɗ����ł���B
����A����70,000�@�̌��Ăƈ���������
https://en.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe German losses, on the other hand, were very high as well. Roughly 12,000 German day fighter pilots were killed or are still missing in action, with a further 6,000 being wounded.
The Zerstorer (destroyer) pilots suffered about 2,800 casualties, either killed or missing in action, plus another 900 wounded in action.
German night fighter losses were also high, in the magnitude of 3,800 pilots or crew members killed or missing and 1,400 wounded.
�����@�p�C���b�g�Ȃǂ������A�h�C�c��R�퓬�@�p�C���b�g��18,600���̐펀�A�s���s���҂�8,300���̐폝�҂������Ă���B
�X�[�p�[�G�[�X���烋�[�L�[�܂Ŗ��ՂȂ��A�]�����o�Ă���Ƃ͂����A
�G�[�X�ƃ��[�L�[�̐�ΓI�Ȕ䗦�����ʂ̃��[�L�[���]���ɂȂ��Ă����������킩��B
�܂�A
>>226 �ŏq�ׂ��Ƃ���
�Ṍw�q���j�x�ɂ���h�C�c�R���A���R�Ɠ����x�̑��Q��^���Ă���������
�u��ʂ̃��[�L�[�p�C���b�g���A���R�@�Ɍ��Ă�������ŏ����̃x�e��������ʂ��グ�Ă������߂ɑP��ł����v���Ƃ�\���Ă���킯���B
������(��߯� Sdfa-hwij) ID:yRKOZyAMd�͊�b�m�����Ȃ��o�J���Ƃ��ؖ����ꂽ�B
���������̗Ǐ����o�J�ɂ͕�̎�������Ƃ����킯����
���Ȃ݂Ƀh�C�c�p�C���b�g�̐�L�ł��ǂ����
>>354 B-29�Ń}�O�l�V�E�������Ȃ̂̓G���W�����i�Ƃ��r�C�^�[�r���Ƃ��ł�?
Me109�̃}�O�l�V�E�������̔����@�˂Ȃ�ĊȒP��������
����W�������~�����̂��A���~�Ƀ}�O�l�V�E����Y�����Ă������Ȃ��E�E�E
R-3350�̓}�O�l�V�E���������g�������Ă悭�R����
���Ȃ������Ƃ����͔̂����@�˂̂��ƂȂ���
�����Ŋm�F�������A�S�̂�24ST�W�������~���i���W�������~���j�ŁA�}�O�l�V�E����������Ȃ���
Me109�̔����@�˂ɂ̓}�O�l�V�E�������̒b�����i�������āA����͓��{�ł͐^���ł��Ȃ������Ƃ����b
Me109���͂��߁A�����@������2〜3���Ԃ���������Ȃ��d�l
���̏c�ʍނ����̂܂ܔ����@�˂ɂ���
He100�͎��p���[��������He112�͂܂Ƃ�����
���21�^�̏ꍇ�A�A�����[�V�������ŕߊl���ꂽ�������
>>364 ���͌y�ʉ��̂��߂Ƀ}�O�l�V�E�������𑽗p�����̂�2������̊J���̎��ɊC���ɂ�镅�H�̖�����������̂ɂ��Ȃ��Ԃ���������
�����炻��̓}�O�l�V�E����������Ȃ��āA�}�O�l�V�E���̊ܗL�ʂ�����葽�߂ȃA���~�����ł��钴�X�W�������~������H
http://a6m232.server-shared.com/298 �z�C�[���Ȃ̓}�O�l�V�E���n�H�A���~�n�H
����s�@�Ń}�O�l�V�E�������̃N�����N�P�[�X�H��̋L�q
https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default& ;BID=F2006090101080962803&ID=M2006090101081462830&REFCODE=C05034563900
�G���W�����͕s��
���ƈ��m��������h�̐��Y�Ɖ��ǂ�簐i���Ă���
�}�O�l�V�E���������̂�1930�N�ォ����{�ł�����Ă邵���Ă���x�������
>>372 �펞���A��O�̓}�O�l�V�E���������G���N�g�����Ə̂��Čy�ʕ��ނƂ��đ��p���Ă���
�l�b�g�����͖��\�ł͂Ȃ�
���M�ł���������̂��G���N�g�����A�}�O�l�V�E�������̓�_��R3350�̎�_������
����ł͌F�{��w�������Ŕ����ɂ����}�O�l�V�E���������J�����Ă�
���㔼�A���{�Ń}�O�l�V�E�������̑�p�ޗ��ɃA���~�������g���Ă�̂����������Ƃ�����萶�Y�K�͊g��ɔ����čH��@�B���s����������H
�����Ƃ��Ă͂ǂ��ɂł����邯�NjM�d�ł͂���
�J�`�J�`�RB29
�A���~�j�E���[���`�E�������Ȃ�
�v������14���ǐ��쐼�ɔ������Ă��痋�d��胄�o���@�̂ɂȂ��Ă��\��������
>>381 ���ꌾ������}�O�l�V�E����������Əd�؍킷��ƔR���邵
B-29�͓�U�s���̒���̗v�ǂƂ������邯��
�܂������̐퓬�@�ɂ͊W�Ȃ����낤���W�������~���n�͍d�����ꂷ��
B-29�͍����ƍq������������
>>386 ���u����̏e���́A�@�̂̋C�����̂��߂���ˁH
���N�푈�̍��͈ꕔ�̋@�̂Ƀ��[�_�[�����t���Ə��킪�t���Ċi�i�ɐ��x���オ��������
>>382 �������痃�^�͌����������\�������������Ɏ������邩�̐��E���������玸�����Ղ����^�Ȃ�Ă͖̂�����
�w�����ł��玸���̗\�����킩�����^�ɉ߂���
�����u���E�U�ċN��������age���܂����X�}�\
������K�V���[�Y�w��������
����̒��J��̊J������
HT���^�ɋ߂��̂̓X�[�p�[�N���e�B�J�����^����Ȃ��ăs�[�L�[���^�ł́H
���^�̏�ʂɋȗ��̑傫�ȕω����Ȃ�ׂ�������2���������A���ɕω�������
>>387 ��Ԃ͎��p�����ׂ���
�����Η͏W���̈�
�v�v�Q�̎��͌�˖h�~�̈�
���W�ґ������܂�g�܂Ȃ������炵������
���B����ɓ�������Ă�����
�����͑����������낤��
���ꂾ�����牓�u����łȂ��Ă��]���^�̑S������e���ł��������A�������]���^���ƍ\����C�����ۂĂȂ�
�U���͂ƌ����Ӗ��ł�PB4Y-2���������ȁH
���Ȃ݂�B-32�͏]���^�̏e���A��������������Ă����^�����͖����ŗʎY�J�n
�R�̖������c�O����
�R��ww2�Ŏg����@�̂ɂ���ɂ�
�����݂����ɏ������˔j���̂�����Ȑ�͍��ɂȂ�����G���W����@�̊J���ɘJ�͎g�����
���ۂɈÎ����u�ɂ͗͂����Ă��炵������
>>396 �����̗^���L���r���͈ꔭ�̔�e�Ŗ��Ӗ��ɂȂ邩��
���u�e���͐��������܂őłĂ邩��
����������Ɏ��p�����Ȃ���
�����̈Î����u�͐ԊO���������œ��{�̂�1km���x�̎��F�������������̂�
>>403 �L108�◧��̃��b�L�[�h�n�h�\�������̍����x�����@�A�L74�̋C�����͍l�����������
�R���̏㓙��6000m���炢�̋C���ō��ΊȈՂ��~���ōς̂ł́H
99���o���y���̓C����^�����e�Ƃ��J�������O����C�R���̗p���ׂ��@�̂������Ǝv����
ki-148�͍ڂ��Ă�������яo�Ă邩��ӊO�ɗg�͂����Ă�r
��햖���ɂ͒P���@���P�D�T�g�����x�����ł���悤�ɂȂ�������
�������ォ��U�����鍂�������@�̓n50���ڂ̃f�u�ŗǂ���
C2�̕��i�����p���H
�Q�P���ߌ�P���R�O������A���e�����s�h���������̐��d�H�Ɗk�H��ŁA���Ђ̒j���]�ƈ��i�T�X�j�����Z���Ύs�[�c�������P�g��������^�̉��~���ɂȂ����B�j���͊s���̕a�@�ɔ������ꂽ����Q���Ԍ�Ɏ��S���m�F���ꂽ�B�����͏o�����V���b�N�B
�e�������ɂ��ƁA���^�͍q��@���i����邽�߂̂��̂ŁA������S���[�g���A����T�T�Z���`�A������X�O�Z���`�B
�j���͍H����̔p�ޒu����ŁA�p��������^���l�Ńg���b�N���牺�낵�Ă����Ƃ���A�����P���[�g���̉ב䂩�痎���������^�̉��~���ɂȂ����Ƃ����B�����ڂ������̌����ׂĂ���B
�鍑�C�R��BT-400�݂����Ȃ̂��J�����ׂ��������A�Ǝv��
���Ƃ̓^�C�j�[�e�B���Ƃ�
>>404 �K�_���J�i���̓W�����O���̒��ɏW���}�C�N���
>>411 BT-400�͂��Ȃ�ڋ߂��ĕ��O��
���Ԃ���퓊������Η����ȏ�̔�Q��H������Ǝv��
���`�A�������
>>414 �P��
���^�I�ȕ��͂͂��邯�nj����o���ĂȂ�����
>>403 ���������]���^�̏e���E�e���ł͏e�g����������J�������ł���̂ŁA��e�Ŕj���ȑO�ɋC���ł��Ȃ�����
���u����e���ł���A���ꎩ�̂͋C�����̊O�ɏo�Ă��邩����Ȃ��킯��
�����Ď��p�������߂Ƃ����Ȃ�AB-17��24�A32�ɂ͂��鑤�ʏe���������Ȃ����͉̂��̂Ȃ�?
���b�L�[�h�n�h�\���̏�㕔�e���ꍇ
https://imgur.com/a/SHQmhCc �{�[���^�[���b�g�̏ꍇ�͂����ƒP�����
�e�g�������͈͂��傫���͂��ɂł����Ԃ��ł��Ă��܂�����C���͕s�\�A�C�������̏���Ƃ͗����ē����������Ȃ��킯��
�ƌ������������C���ɂ���
>>420 ����A������B-29�̉��u����e���͂����Ȃ��Ă�Ə�������
>>420 ����㔼�͈Ⴄ�̂�?���́u�e���v���Ă̂͋@�e�肪�����ďƏ����Ă�ꏊ�Ȃ̂��A�@�e�����߂��e���̂��ƂȂ̂��H
�O�҂ł����B-29�ł���Ă�A�C�������ɏe�肪���ċC�����O�̋@�e�������u����Ƃ����V�X�e���A
��҂��Ƃ���@�e�肾�����C�����Ƃ̍s�������ł����A�����ԓ����Ȃ���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���肦�Ȃ�
93�o�y�݂����ȏe���ŃC���[�W���Ă�
�T�C�p�����A�O�A�����A�e�j�A�������瓌���܂ł͕Г�7���ԁA���̂����ǂ̂��炢�̎��ԍ��X�x�ɂ���̂��s�������A
�Ȃ����[���b�p�ɂ�����B-17�̔������x��7000m���炢�ŁA�S�����_�f�}�X�N�Ɋv�W�������p�őς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A
���Ă̍q���͉��B�̍q���Ǝ������Ⴄ���x���ʼn������Ȃ����ɍŌ�܂Ŋ�������
��ꎟ���̍�����d�M���͎g���Ă邪�p�ɂɌ̏Ⴕ�Ċ��d��Ώ������������炵��
���܂�g�����Ȃ�Ȃ��̂ŏ��ւ�R�炵�Ă��܂��A����ŘR�d�����Ȃ�ė���������Ƃ�
�b�͕ς�邯�Ǔ��{�̊C�ݐ��͒���������s�D�ʼn��݊Ď��Ƃ��𗧂�����������
���{�̏ꍇ�A�䕗������Ƃ�
�A�����J�͈̂�x����U�{�[�g�Ɛ���āA��C�ŕԂ蓢���ɂ����Ă������
���{����w���E���o�Ȃ��̂���肩��
>>433 1944�N�Ă܂łȂ�A�Ȃ���
���{�A���쏔���A��p�A�䓇�A�V���K�|�[���܂�
���s�D�ŏ���������ł͂Ȃ��낤��
>>435 �����z�肵���R���͂��ԂĂȂ������E�E�E
>>435 ���{�ߊC�ň�Ԑ����͂ɂ���Q�̑傫�������ɂ��Ȃ���A�Ӗ���������
>>437 ���Ǝc���N�Ŕs�킷�鎞���ȍ~�Ɏg���Ȃ����疳�Ӗ����Ǝ咣���闝�R���悭������Ȃ�
����◰�����������܂ł�
���{�R����s�D�ɂ�鏣�����\�Ȏ����ɁA�{�y�ߊC�ŕĐ����͂��������ĂȂ�����A���ʓI�ɖ��ʂȂ̂ł�?
���s�D���X�e���X������Ȃ烏���`��������
>>440 �ꉞ���䂪��������Ă͂��邪
�A�����J�̑ΐ�������s�D�̓��[�_�[��MAD�𓋍ڂ��Ă������A���{�ł���������ϖڎ��Ȃ낤��
���I�^�̎R����1942�N�ɓ��{�ߊC�Ő����͂Ɍ�������Ă�
���s�D
>>443 ���C��MAD�����Ă����@�̂̐��\������ڂ������̂�
�قƂ�NJ��ĂȂ�
���C�͓o�ꎞ�����x������̂����
1944�N8���ɒ��ǂ��V�����Ő����͂Ɍ������ꂽ
�ē����x�̍����\�������C�łȂ犈��ł���������
����ȍ~���ʂ������đ䕗���ʂ�ӂ�ŁA��Ȃ�Ďg����̂��ˁH
>>416 ���ʊJ���e���̑����
���u�e���Ȃ�
�ғ��悪�P�W�O�x�܂ʼn\������
�㕔�E�����e���ő��ʂ̑Ώ����ł���
�V���K�|�[������o�[�V�[�C���A���V�i�C������̍q�H�т�20�@���炢���s�D���ׂĊĎ����銴���H
�}�[�V�����ƃt���}���g���̐����͊�n�����邩�A�@�����T�������Ȃ��Ǝv��
��s�D���ƁA�t�ɕ��サ�Ă��ă{�t�H�[�Y�S�O�����̉a�H�ɂȂ肻������
�吼�m�Ȃ�h�C�c�R�͋�ꎝ���ĂȂ����炢�����낤���Ǒ����m���Ɣ�s�D�͂���B
>>451 ����A����̍L���㉺�̑S������e����B-17��B-24�ɂ������āA����ɉ����đ��ʏe�����������̂ɁA���̌��炵���H���Ęb�Ȃ�
�܂�B-17��24�̂悤�ȑ��ʂɎl�p���J�������e����APB4Y-2�̂悤�ȃu���X�^�[���e�����ƁA�C���ł��Ȃ�����Ȃ낤����
�����e���̗D��x�����X�����Ȃ��\�������邩��
���C�̎���ʂ��C�}�C�`�Ȃ̂͋@�̐��\����Ȃ��ď����͈͂��L���������炾�낤
���Ɖ��u���쎮�ɂ��������ЂƂ̗��R�́A�A�i���O�R���s���[�^�ɂ�錩�z���ˌ��̂ł��鍂�x�ȏƏ���
>>456 ���ʂ��ƕБ���������o���Ȃ��Ƃ�����͎�C�̕ϑJ�݂����ȗ����H
�ǂ����{�b�N�X�Ō݂��ɃJ�o�[����̑O���ނ�݂ɑ��ʑ��₵�Ă��˂�
>>453 �D�c���ʉ߂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��C����r����������铇�̂Ȃ��吼�m����
�D�c�̌o�H�������_���ɕς��Đ����͂ɑΏ�������@�����邯��
���{�Ɠ�����Ə����̔z�u��C�����ǂ����Ă��D�c���ʉ߂��ׂ��댯�C��ɂȂ邩��
�펞�A�o�[�V�[�C���Ƃ���p�C���A���쏔�������ɖ��ȏ������݂���
�N�����Ă��������͂��A���q�������邱�ƂōU���@������炷�̂͌��ʂ�����
�����푈��L���ɐi�߂邽�߂ɂ́A�h�C�c�Ƃ̓������s���ŁA�h�C�c�ɂ͒����x�������������Ă��炢�A
�o���@�Ƃ��Ă͈ٗ�̑؋Ԃ��ւ闤�U�������Ă��̂�����
�����̌����Ȃ���^�o���@�̈ꎮ���U�ŏ������Ă������T�m�Ŕ������Ă��A���̒n�_�ɖ߂��Ă���܂łɐ����ďI���
B-29�̉��u����@�e���̋��瓮��
VIDEO �u�V�X�e�����\������O�v�f���v�u�I�[�C�F�[�A�Ə���A���ʔ��A�@�e�H�v�u���ʔ�����Ȃ���W���[�A�R���s���[�^���v
�]���̐���@�e�Ƃ̎d�g�݂̈Ⴂ�Ƒ���@��������A�j�����킴�킴����Ă��܂��A�A�����J����ɂ͂��Ȃ��̂�
>>464 ���Ⓦ�C���z�������O�A1943�N12���Ґ��̑�901�q����̋�Z���U���AMAD���ڂ����ΐ������@�ɂȂ��Ă邯�ǂ�
�A�����J���ƃ��b�L�[�h�E�n�h�\���n�̔��W�^�o���@��AB-24���甭�W����.PB4Y-2���ΐ������@�����A���������
�@������������{�̗��U�N���X������Ă��S�����������͂Ȃ����H
�Ȃ������X�[�p�[�G���N�g�����q�@�������n�h�\������A���̌����^�̃��[�h�X�^�[���q�@���甭�W�������F���`�����A�n�[�v�[���ɔ��W���邪�A
>>466 ��p�Ό��ʓI�ɂ낭�Ȃ���Ȃ�����
�������̃m�E�n�E�͓��C�Ɉ����p���ꂽ���낤���A
���U�̓ݏd������ڎ��Ŕ������Ă��̂܂ܔ������Ƃ��Ȃ���
���C������Ă��悤�Ȑ�ʂ͏o�Ȃ�
���Ƃ͓��{���U�ƕĔ����@�ł͔��e���ڗʂ�5�`10�{�Ⴄ�̂ŕČR�@�̗���o���ē��{�R���o�����͂��ƌ����̂͘_�O
>>465 �ĕ��͖����A�C�X�N���[����H�ׂ����Ȃ��Ɛ킦�Ȃ����炢������()
�����A�j���ł���_�C�������Ȃ���G�@��Ǐ]���ăg���K�[�����Ƃ��^�R����Ȃ����疳���I
����Ԃ̉^�]���ł���Ȃ炻�ꂭ�炢�ł���͂��I
�ċ�Ɏ��ۂ̏Ə����삪������������Ɨ������Ă�͈̂̂��Ǝv��
���C�̖��_�͒ᑬ�߂��ď����\����܂ōs���̂Ɏ��Ԃ�������̂Ƃ��̂��߈��̏�����悪�L���Ȃ�
���C�̓G���W���̔n�͂�������610hp�~2�A�ő呬�x320km/h�ƁA��Z���U��O�^��416km/h��肸���ƒx���A�@�q�Ȃ킯�ł��Ȃ�����
�ΐ������@�͍��w���ł���Ă邭�炢�ŁA�������͒ᑬ�ȕ����L��
���U���ݏd�Ƃ��s���Ă����Ȃ���A�x���ق��������Ƃ�w
>>468 ��p�Ό��ʓI�ɂ낭�Ȃ���Ȃ�����
���Ă̂��Ӗ��s���A���U�Ƃ��Ă͋��������āA������A���A��Ԕ����ɓ]�p���ꂽ�@�̂��A
�킴�킴�V����150�@���������s�@���R�X�p���ǂ��H
�Ȃ����U��O�^�̏��q���x150km/h�ł̍q�������͓��C�̖�O�{�A�ŕ�892�~�̐����ǂޒ��x�ł킩�邱��
�����F�킴�킴�V����150�@���������s�@���R�X�p�������H
�܂������_�j�����u���w���̎v�������x���̒����퐄���v���n�߂��̂͐����N��
96�����U�̋@�����������炵�������̂ɉ������Ďg���������悩�����ȁB
�ǂ��������_�j�Ȃ̂��H�Ƃ肠���������Ώ����Ƃ����A�{�N�������l��������N
��1000�~�����Ȃ�����
��Z���U��O�^�̏��q���x150km/h���A�ΐ������ɏ[���Ȓᑬ�ł͂Ȃ��Ƃ��������H
���A���߂�A������Ȃ�ł��x�������Ǝv������A�C�R�@�Ȃ��150�m�b�g�i278km/h�j��������A�܂������p�Ƃ��ď[���Ȓx��������
�Ȃ��A��͂�ߊC�ł̏����C���ɂ��Ă����㎵���͍U���Ə��q���x263km/h�A
�����͂�T���Ď�������Ȃ瑬�x���K�v������
���s�D�͋����Ɏア����Ȃ��A�V��������\�o����A�����ɋA�҂������邵
>>484 �ł��D�c�̏�ɒ���t���Čx�����Ă��s�D�́A����������ǂ��������ł́H
��s�D�����ăA�^����t���āA��ɐڋ߂���Ηǂ������E�E�E���Ď��ɂȂ肻��
�吼�m�̃A�����J�C�M���X�q�H�̗l�Ȓ���Ȃ���Ɠ������x���œ��{���q�H�G�Ɏ����Ă����ǂ�
�ŁA���ׂĂ݂���C�M���X�͑�ꎟ���ŁA�D�c��q�p��SSZ�����s�D���J���E�^�p���Ă����Ɣ���
����V�X�e��������P�̂̐��\�������⊮��������Ηǂ��ˁH
����q�@�Z�p�̖��n�ȃp�C���b�g��m��P������̂͊�Ȃ�����
���U�Ɗ͍U���\�������ŃK�o�K�o�Ə��Ղ����̂őΐ������ɕK�v�ȋ@�ނ��l�������Ȃ��Ȃ���
>>491 ���������O�q�̑�901�q����ȑO�ɁA�����͎�肪���̕����������������x���Ȃ�A���{�C�R
���{�̐��͌��܂ŏo�ė����قǑ��̒����A�����J�̑ΐ������@�ƂȂ��.PB4Y-2�ɂȂ邪�A
�m�[�}����B-24�����Η͂������Ė��ȑ��肾
>>469 ���{���U�ƕĔ����@�ł͔��e���ڗʂ�5�`10�{�Ⴄ�̂�
�����A�{���ɊO���@�ɋ����������������������ĂȂ����Ă̂��܂�킩��ȋY�������
���U�̒ʏ픚�e���ڗ�500�`800kg�ɑ��A�i�ő哋�ڗʂł͂Ȃ�����Œʏ퓋�ڂ���ʂ́j
�Ⴆ�Α����m���ʂő�\�I��B-25��100�|���h���e�~24��1080kg�A250�|���h���e�~8��904kg�A
�܂���650�|���h���e�~3��885kg�A�����5�`10�{�Ȃ�ł����H�n�A
PB4Y-2�̏e���z�u�͗��z�I����
�Ȃ�����ɂ��w���o����̂Ő^���ɂ͔����E���E��6���̃u���[�j���O���w���o����
99��1����2���ŃK�b�`�K�`�Ɍł߂Ă�͂��̌���^�ꎮ���U��
PB4Y-2�͒����ɂ��Ĕr�C�^�[�r���͉��낵�āA�����Ɩh��������������A
>>490 �ĉp�R�͖��n�ȃp�C���b�g��P�@��
���ɂ悭�g���Ă�����
������Ȃ�ł͂̍�킾��
�����@���m�̌��������őΐ���킪�j�Q�����ƂȂ��
���U���ǂ�ǂ�G�̔�s���͒������j���Ă����Ȃ炢������
���U���͏�ɉX������ʂ���Ă����
��������ʋy�є�Q�\(�푔�^)
���U���z�����ꂽ�q����ɂ��Ē��ׂ���A26�̕����̓��A��O����풆�ɉ�̂ⓝ���A
�ނ���B-26���ꎮ���U��2�{���炢�������Y����ĂȂ����Ă̂͊���ƈӊO�ł͂���B
�������ł����č�����B-24������18000�@�ȏ�Ƃ��A������������
>>465 >>470 �����ɓ��ł������ȊJ���҂������̍l���t����w�Ďv���č�����𗧂������킾��w
���N�`���[�t�B��������Ă�z���������ĂĒ������Ă���w
����ȕ��݂����Ȏg�������œ����镪���Ȃ�ww
B-29�̋@�e���P-51����q�ɕt���悤�ɂȂ��Ăǂꂪ�G��������������Ȃ��Ȃ������ĒQ���Ă�̂�
�@��܂Ŕ��ʂ��ēG�����������������G�@�̃T�C�Y�ɃQ�[�W���킹��Ƃ�ww
����ɎԂŃK�[���t�����h�ƃC�`���C�`�����Ȃ���^�]�ł������g����͂����Ƃ�w
�n�C�e�N�����ǂ��납���_�_�ɂȂ��Ăĕ������^ww
�Ƃ͌������{�P���퓬�@�͓�P�������ė������܂�ς���
�A�z����w
>>505 �w�̂���p�C���b�g�Ƃ͕ʂɁA��������Ă����L�ۖ��ۂ̓c�ɂ̌Z�����B�ɁA���u����@�e�̊T�O��@�����ނ��߂̕�������A����Ő���
����300m��1���A�܂�30m�������ԈႤ�Ƃ���
>>509 ���O�̃I�c�����c�O�Ȃ͕̂�������w
�e�����B����̂��덷�����瓖�����Ȃ��Č덷�ʼn���������Ԃɒe�����B���邩�瓖����Ȃ���w
����������^
VIDEO �V�X�e���𗝉����ĂȂ��A����̃A�z�̂��߂̂�����蓮��
>>512 ��剻����Ȃ�����ԈႢ�⊨�Ⴂ�������up�傪�������Ă銨�Ⴂ���悪�����Ƃ�w
����()������̓C�P��Ǝv���č����������c�O�V�X�e���Ȃ���f�l���x������w
�����ɁA���̌�B-36�ł��g���Ă�V�X�e���Ȃ��ǁA�f�l������̓_�����ƌ�����鎩�M�͂ǂ����痈��̂��ˁH
�ʂɃE���R�ł����肪�����Ȃ�t���邾��
B-32�Ȃ�Ƃ�����B-36���炢���ƃ��[�_�[�����t���ɂȂ��Ă��Ȃ��́H
VIDEO �����Ďˌ��V�~�����[�^�[�����炢�[�����Ă����A�����J�R
�܂�������V�����撣���Ă������ł͋@��ǂ��납�G�������ʂ���������̂�����w
>>500 ��s��U���ɕ��i�g���ł��邩�H
�Ƃ����Ƃ��Ȃ�������킯�ŁA�X������ʂ������Ă��炤�ׂ����핺��Ƃ��ĉ����Ă����ׂ��Ȃ̂ł́H
���U�̏��Ղ����ɍ���Ȃ��A�q�Ő�Ɏg���Ȃ��A�琬���ǂ����Ȃ��Ƃ����͎̂x�ߎ��ςł����e���ł���P�Ƃ��ďオ���Ă��Ă�킯�ł���
�͑����킩�����Ɨ��ɒ[�ȔC���Ɍ����Ă邱�Ƃ͂킩���Ă��͂�
���U�͑o��������G���W������������H����
�P���@�̊����𑝂₵�āA�O���ł̉ғ����Ɠ������҂��ł��̂̓\�A
�C���p�[���ł́A�p��R�͑�5�t�c�܂�G���E�A�����C���Ńh�C�c�R�Ɛ퓬�o���̂��鐸�s�������_�R�^30�@�ŋ�A�B����ɂ��틵����ς�����
�A���@�Ȃ�9�C�����炢�̈����ĎO�H��������Ȃ��Ă����锭���@��
�ǂ�ǂ�̂Ă�Ƃ������A�ė����Ɏx�Ⴊ����@�̂͏C�U�����A���̋@�ɂ�鎟�̕ւ̂��߂ɘe�ɐς�ǂ�
�ꎮ���U�͔�s�@�Ƃ��Ă͋ɂ߂ėD�G����H
B-29�������O�̃f�B�Z���g�ɓ��������q��P-51���ǂ����Ȃ��Ė��q�ɂȂ�b�͌���
�ꎮ���U��l���A�����ݕ��A���@�Ƃ��Đ��Y����Ηǂ�
�ʉ_�݂����ɗ���w�ǔR���^���N�ɂ���
>>525 ��̏�ł͐�ɉ����̐��ɓ�������������
�o�|�R�W�͍����x�ł͑�����
���ł̓^�[�r�������ׂɂȂ蓮���͓݂�
�ł��A�ꎮ�̐������x���ĂT�O�O���^�����x����
�n�͌����A���т̐������Ŋ��B�����Ȃ��B�����30�x�ȏ�E�����̊��ɎN���ƃo�^�o�^�|��Ă����B�����̈�ʏ펯�ł��邪�R���ɕ������������Ă������Z�ɂ͒m��悵�����������B�⋋�y���ł͂Ȃ��A�u��ʋ��{�y���v�̈�Ȃ̂��B
���U�Ɋւ��Ă͂���������s��݉c�\�͂Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ӗ�������
�A�h�~���E�{�b�N�X(�~���w�n���邢�͗��̐w�n)�B
���������̘b�A
>>492 �������A�{���ɊO���@�ɋ����������������������ĂȂ����Ă̂��܂�킩��ȋY�������
����()�����ĂĂ�
>>466-467 ���������A�Ȃ��ĊC�R��PB4Y-1��ΐ������Ɏg���Ă����������ĂȂ��j���J���Ƃ������Ƃ͂������������
�j���J����Ȃ�������B-17��J�^���i��s������̕ČR�̑ΐ������^�p�Ɠ��C�̉^�p�̈Ⴂ���������Ă�͂�������A
�����������@������������{�̗��U�N���X������Ă��S�����������͂Ȃ����H
�����������ڒ����Ȃ��ƌ����킯���Ȃ�
�A�����J����PV-1��2�A�C�M���X���Ɨl�X�ȑʍ�@�������C���ɋ��o����Ă����̂��m��Ȃ��킯����
�A���C���ɂ����g���̂Ăł���悤�ȋ@�̂��K�v���Ǝv��
�j���[�u���e�����͗Ǎ`������������܂��}�V��
���V���g�����œ��ׂ̊J������������A���̌㏺�a12�N����A�����J�Ɣ�s��݉c���[�X�����Ă邩��
�L115����̎��ɗ]���Ă�400��̃n115��]�p��������wiki�ɂ��邯��
�Ƃ܂����̍ۂ��y�ւɎg����A�O����̔����@��������A���@�܂��͗A����s��������Ώd���Ƃ�����
>>537 ����퓬�@�������g�p�������N�i�C�̓���s���
���U���g�p�����̂̓u�i�J�i�E�̐���s��
>>541 ��s��͓�Ƃ����X������
�܂������{���j���[�u���e�������̂��ē�T�Ԃō�����Ǝ咣����̂��E�E�E
�ΎR�D�ɖ����ꂽ�͓̂���s��Ƃ����w�E��
���^��s���Ƃ��厸�s���
>>534 �܂�Œ��U�̌�p�ɔz�����ꂽ�A��n�͂̓ݑ��@�ł��铌�C�ɁA�@���͂�Η͂����邩�̂悤�ȕ���������
�u�ΐ������ɂ͂Ƃ肠�������e���ς߂āA�����������s�@�Ȃ�Ȃ�ł��悩�����̂Łv�i�����������j
�ČR�͗A���@���甭�W�������|���R�c�@B-18��MAD�𓋍ڂ��ē��C�݂�J���u�C�ł̏����Ɏg�p
An2���ǂ��̃n115���ڂ̕��t�A���@���ăW�������~���g�킸��
>>545 DC2�h���@�Ȃ��100���A���@�Ȃ݂��ґ�����Ȃ��ł����I
>>100 ���A���@�Ȃ݂��ґ�
�ނ���ꎮ�ݕ��A���@�����b�L�[�h L-14 �X�[�p�[�G���N�g�����n�h�\�������@�̕����߂�����
>>545 �ڋq�ɕK�v����������>�\�[�h�t�B�b�V��
��q���ɓ��ڂ��Ă̑D�c��q�Ȃ�܂������A���ォ��̔��i�̏����ōq��������880km�ł́c
�u�͂��߂͎��d��������Ȃ��̂ŁA���d�������W�߂ČP���Ɏg���Ă��܂����B
>>549 ���̒Z���\�[�h�t�B�b�V���ɂ͋�ꂪ�K�{�������킯�ŁA���D��ꂩ�瑽���̎����ł��Z�߂̔�s�b����J�^�p���g�����ŗ��͏o�������犈��ł���
�������킩���ĂȂ��j���J���Ɓu�\�[�h�t�B�b�V�����o�������ƂȂ���{�R�̒��U�ɂ��o�����v�Ȃ�ēڒ����Ȃ��Ƃ��������Ⴄ�݂���
>>551 �C�R���ґ��퓬�n�߂��̂���44�N���납�炩�B
���R��42�N���炵�Ă��̂Ɣ�גx������B
��풆�ɕĊC�R�ɔz�����ꂽPV-1��1600�@�A�����A�����[�V�������ʂ̕�����PV-2�ɍX�V���ꂽ
���{�͗��C�R���ɐ�O����ґ���킵�Ă�
>>552 ���C�Â������A�܂�����Z�͍U�𒆍U�Ɠǂ݈Ⴆ�ăg���`�L�Ȏ������Ă�H
>>553 �i����u���̋����C�R�ƈ���ė��R�̓t�B���s�����100���Ԃ��傢�̃p�C���b�g���荞�ޗl�Ȓi�K�ł����߂Ă��̃��b�e��@�ɂ͓��ʂ̔z�����Ȃ���Ă����B
�Ⴆ�t�B���s���̔�s��31���(�ꎮ�퓬�@)�Ȃ̃p�C���b�g�͒Z����s�P���̒��ŒP�@�i���̌P���͂����ґ����̋��炵���Ă��Ȃ������Ɛ���j�ɂ���A�Ɨ��j�Q���ɏ����Ă�����
���̑��肱���̃p�C���b�g�͊i���ɓ�������܂�Ŏ��������Ȃ�����
�ނ炪�������ׂ��͎l���킾�����̂�
>>556 ���[
>>466 �́u1943�N12���Ґ��̑�901�q����̋�Z���U���AMAD���ڂ����ΐ������@�ɂȂ��Ă邯�ǂȁv�̉����Řb�����Ă�̂��Ǝv������
����ɂ���A���U�����㔭�i�̑o�������������@�Ƃ��ĕs�K�i�Ƃ����咣�͈Ӗ��s�������ǂ�
���ǂ͎����̂Ȃ����{�͏����E��@�ɋ@����������
>>553 �C�R�̖����d�b���g����悤�ɂȂ����̂�44�N��������
������O�|���͖�������Ȃ����Ǝv��
�A�����J���i��ł��͈̂Í���ǂ����ŏ����W���͂̓E���R���������ǂ�
>>559 ����͂��̎咣�̎d�����u�ĉp��(PB4Y-2��)����Ă�������{�̒��U�ł��\���v�Ƃ䂤�q���݂����Ș_�@�������
����ɑ���u���e���ڗʂ�5�`10�{�Ⴄ�v
�ɑ��锽�_���u(�Ԃɍ����̒����������p��)PB4Y-1�̓��ڗʁv���ɏo���b��P���Ȃ��āA�c�_�ɂȂ��
���ꂽ�ˁA�ČR�̉^�p���Ă��������@��PB4Y�n�������Ƃł��v���Ă��̂��H
�����͂ǂ̂��炢�̍q�������Ɨ��������邩�ɂ���
PV-1���F���`�����ɂ�锚�e���ڂ̈��
500�|���h���e�~2��250�|���h���e�~4�A���v2000�|���h�i907kg�j�A�ő哋�ڗʂł������1.5�{�܂Őς߂邪�A
����ł���Ȃɐςނ��Ƃ͂܂�����
�t�Ɉꎮ���U�̓J�^���O�X�y�b�N�ł͓��ڗ�1t�ƂȂ��Ă��邪�A�ő哋�ڏd�ʂȂ�2.2t�i�����ԁj���Ă��ƂɂȂ邵��
���R�̖����͂��Ȃ�g�����炵����
�G���W���̓_�Όn����̃m�C�Y��̍���A�A�[�X�̕s���������炵��
���U���R��̈���������ΐ��ł��̍q���͂�����
����ƃK�\�����H�����Ⴄ�ƌ������������ł���������
�ꎮ���U�Ŗ��ڂȂ�6000L���炢�A200L�h������30��
���������ŕ����@�A�����ΐ������C���Ŏg���ƂȂ�Ƃ�����Ɛh����ł�
>>567 ���Ȃ����̋L�������ǁA�Ȃ��Ȃ��ʔ�������
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/82917?page=5 �ČR�̖������K�_���J�i���ӂ�܂ł̓_���_���ō�䎁�ɗ��Ƃ��ꂽ�T�U�[�����h����
>>569 ����������o������A���q���̔R��̗ǂ��h���ڂ̋㎵�͍U�����@�ނ��Ȃ��Ȃ�
�����đ�햖���ɓ��C���o�Ă��鍠�ɂ͓G�@���o�Ă��������I�ɐH���邾���A
���ۏI��܂łɐ��Y�@�̖��������Ă���
>>569 �����ɕČR���ŏ��̕��ŋN���������ɍ����Ώ����Ă�Ⴀ�ȁB
�����������J�[�X�Ƃ�������Ă��݂����ɍq��p�f�B�[�[���G���W���ł��J�����Ă�Ⴀ�A��p�̏����@�����Ӗ��͑傫������
�̂̍q��p�f�B�[�[���Ƃ����b�`�������������
>>574 �a�n�a�̏����܂Ŋ���o���Ă����݂�������
�X�s�b�g�t�@�C�A�[�ɍ����x�^���ł���
����̏ꂪ���V�A����݂̂ɂȂ�������
�R���ɂ����y�����Ă����͓̂��{�@�ɂ͗L��
Do18�Ƃ�Bv138�Ƃ��̔�s���ł��̗p����A�����̍q�������������������A�ĊO�����邩������Ȃ�
���{�̓a�[�[���̗p�卑�ł͂���������
���āA���̃n22����92���d���̃A�����E�E�E
�X�Q���d���̂��āA�R���s�X�g���̂��ꂩ�E�E�E
>>564 ���ꂽ�͉̂��̕��A�푈�Ƃ����̂́A�����@�̌`���ƊJ�������̋߂����̓��m�ōs���ƌ��܂��Ă�̂��H
��������b�퉳�픚���@�U���@�����@�Ƃ�����ʂ����Ӗ����Ȃ���ȁA�U���@�͍U���@�Ƃ�����r�ł����A�����@�͏����@�ȊO�Ƃ͔�r���Ă͂Ȃ�Ȃ��H
�������̓��̈������w���݂����ț������͂�
���������O�ɁA���{�ꋳ�炩���蒼���Ă���
����ȑO�ɋ@�̃f�[�^�����{�R���ǂ������^�p��������S���������ĂȂ�����A���U��X�U�͔��őΐ������Ȃ�Ē������������t����낤��
�����ɍڂ��Ă邱�ƈȊO�͑S���m��Ȃ��}�E���g�~�قǒp���������������͒�����
��d���̈ꕔ�̋@�̂ɍڂ����̂́A�h�C�c�Ō�������204Ju86��Do18�ABv138���Ɏg��ꂽ�̂��A���̌�p�ł��郆��205
>>581 �ČR�̎g�p�����̂́A���o�������@�ŏ����@�Ƃ��ē]�p���ꂽ���̂���A���U�Ə������������̂����Ȃ����H
�{���ɊO���@�ɑ���m�����S��������
�Ȃ��x���`����/�n�[�v�[���ɂ���B-25�ɂ���A�����^�̃x�[�X�ƂȂ����o�������@�̓��ڗʂ�3000�|���h�i1360kg�j
�����ɂ́u�@�̃f�[�^�����ڂ��ĂȂ�����w�d�T�⎥�T�ɂ��āx�w�^�p���@�ɂ��āx�͒m��Ȃ��ē��R�v�݂����ȊJ�����肪������
����A�킩�������瑁��5�`10�{�̓��ڗʂ̂���@�̂����Ȃ̂������Ă�
>>�@�����ɂ́u�@�̃f�[�^�����ڂ��ĂȂ�����w�d�T�⎥�T�ɂ��āx�w�^�p���@�ɂ��āx�͒m��Ȃ��ē��R�v�݂����ȊJ�����肪����
���`��4���@���m�Ƃ�������őΐ������@�Ƃ������薳���Ȃ�A��O����PB4Y-2�Ɠ���̒��ڑΌ����������悤����
>>�T�M�Z�p�����n�ł͐�ʂ͏グ���Ȃ�
�u�����A�āv���ď��w�����w���̃}�E���g�~����A�q��t�@���Ƃ����ʂ͒x���Ƃ����Z�����炢�ő��Ƃ�����
>>588 5�`10�{�̓��ڗʂ̘b�͂ǂ��ɍs�����̂��ȁH
�Ȃ��������Ȃ�����Wikipedia�̐����Ō���Ă�悤�����ǁA�ΐ������C���ŗ����ɔ��e�Ȃς܂Ȃ���
�����B-24D�ȍ~�̃^�C�v�ŒZ���������C���̎��ƁA�Ί͍U���^��PB4Y-2B���O���C�_�[�U�����e�𓋍�
����ꍇ�i���햢�g�p�j���������H
����B-24/PB4Y�̕W���I�Ȕ��e���ڗʂ́A�ł������g��ꂽ500�|���h���e�̏ꍇ��12���i2722kg�j�A
�J�^���O�f�[�^�����Ō���Ă�̂͂ǂ����Ȃ�
>>590 ���O�O�b���Ă���ƒm������ł��ˁA�������킩��₷��
>>589 ����901�����������������͂킩�邪�A
��Z���U��O�^�ƁA�㎵����i�����炭�́j��O�^�ŁA�Ƃ����͎̂�����������
������H-6�d�T��KMX���T�ɂ���wiki�œǂ���̃��x���̃j���J�m���Ō���Ă�l�q����ɂƂ�悤�ɂ킩�邗
>>591 ���O�ɗL���Ȃ悤�ɔ���ł��b���Ă������̂�
���ď����@�Ŕ�r�������Ȃ�A�����ŗ�o�����@�̂�[���s���܂Ŏ����Ŕ�r������ǂ�
�ŁA�����ɊԈ���Ă�킯�ł����A�������m���������Ƃ���������F�߂悤��
>>593 901��Ґ������̑���������2�@��ŁA��N���炢��͋@�Ƃ��ĉ^�p����Ă���H
���ꂩ�瓌�C��1944�N10���ɍ����C�R�q����ɔz���A901��ւ̔z���͂���ȍ~
������Ɠ˂����܂��Ƃ����b��炷�Ȃ�߂��ق����ǂ���
���Ґ������̎�͂͋�Z���U��O�^�ƁA�㎵����i�����炭�́j��O�^
���������ĂȂ��A�����̒m��Ȃ����̂͑��݂��Ȃ��I���G�̐l�����w
�Ќ𐫊F���̃L���I�^�ɂƂ��Ă͐����������X�e�[�^�X�Ȃ̂��ȁH
�������x�̂���y���i�Ȏ������Ȃ��̂��A�Ɣ�����Ă�̂ɁA�ȂႤ�Ӗ��ɔ]���ϊ����Ă�悱����
�������ďڂ����ӂ肵�Ȃ��Ă���
>>466 >>475 ���̂�����̃��X��ǂ߂A�j���J�Ȃ̂͂����킩��
���e�̓��ڗʂ����{�@��5�`10�{�̕ČR�@�̏��̓}�_�`�H
PB4Y-2�Ɠ��C�Ŕ�r���Ă݂�Ⴂ�������
���{�����Z�g��H-6�d�T���ڎn�߂�O����ČR�͋ɒ��Z�g���[�_�[�g���Ă邩���
��Z���U�͑ΐ������@�Ƃ��ĕs�K�i�A�Ȃ��Ȃ�c���܂Ƃ��ɐ����ł��������]�Ȑ܂��������������̉��A��
���������A�ČR�Ɠ��{�R�̋@�ނ̐��\���Ȃ�āA�S������Ă܂���ł������H
�Ȃ�ł��ڂ��Ă鐢���Œ��ׂ�Ηǂ���ˁH
�Ńj���J�����N�͎����Ŏ����̔ᔻ���n�߂�
>>602 �ɖ߂�Ƃ��������̃��[�v�p�^�[��
�������Ȃ���l�b�g����̏����W�����r���[�A����ł��āu�{�N�������v�����v���Ƃ͐�A
���[�v�Ǝ��ȏЉ�n�܂�܂ł��S�[���f���p�^�[����
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�Ɣے肷��ƃE�\�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA����ɂ͓����Ȃ��̂͗��h�ł�w
MAD�͐��ʉ��̐����͂�T�m���邽�߂̃��m�Ȃ�Ő���ڕW�����T�m�ł��Ȃ����[�_�[�Ƃ͗p�r���Ⴄ
�Ε����[�_�[�ő{�����č����̂܂܌������ă��P�b�g�e�ł����ޕČR��
PV-1/2�Ȃ�܂������APB4Y�Ƀ��P�b�g�e�^�p���͂͂Ȃ���ł���w
����
�X�ɔ�s���͍\����A���̓��ɔ��e�q��ݒu�ł����A�����ɓ˂邷���ɔ��e�����ڂł��Ȃ��킯�ŁA
�o�J������Ȃ�̂��߂̖������킩���ĂȂ��炵����
�����������X�O�ɐ����������Ƃ�x�X�Y���o�J�̑���͎��Ԃ̖��ʂł��������Ȃ�
�X�ɂ������c����͒ʏ퓋�ڗʂ���800kg�̔��e��������2���Ōv1600kg�����ǁA
�����͓��{���ł��}�C�N���g�Ή��̋t�T�t���Ă邩�烌�[�_�[�Ō�����O�ɐ����Ă�\��������
�q���������������Ȃ��J�^���O�X�y�b�N�������Ē��U��5〜10�{�̓��ڗʂƂ��������Ⴄ�̂͒��x����߂��ł́H
���{�@���悭�w�E����铋�ڗ͂̒Ⴓ�����q���͕ʂɂ���ƑS���Ⴄ�����������Ă�����Ă̂͂��炭�O���猾���Ƃ�ȁB
�������ׂ��h�䑕����d�q�����ڂ��Ȃ���q���������炢�L�т���
�Đ��͑�풆���ȍ~�͂Q�O�����A�S�O������@�֖C
���ƔR���������A�ǂꂾ���J�^���O�X�y�b�N�ɋ߂����\�o������
>>618 �吼�m�͓������Ȃ��̂ŗ��㏣�����͂��Ȃ��C��ł̓Ɛ��̃E���t�p�b�N���������̂ŃM���b�v�߂邽�߂�
���ɗ��R�@�Ƃ��i���z�G�ł���\�A��R�Ɠ����Łj���^���e�œG��s����p��������Ƃ��ɓ������Ă��ŁA
>>625 �\�����P����5�C���`�C�͂Ƃ������A�|���|���C�͉��Q�ɑς��Ă����Ɠ������̂��ˁH
20mm�Ȃ���O���Ċ͓��Ɏ��[�ł��邾�낤��
>>627-628 ���{���R�ł������ۂƂ��_�B�ۂ�����������Ȃ�
���̓_�ł��C�R�̍����Ԃ肪�킩��
>>630 �|���|���C�iQF 2�|���h�j�ς�ł�A�����J�����͂͂˂���A40mm�{�t�H�[�X����
�܂��������ۂ�_�B�ۂ���q��ꂾ�Ȃ�Ďv���ĂȂ���ȁH
���ƒ���2.2m�A�d��68kg�̃G���R��SS���A�}�����q�ƌ����ĖC�˂�����O���f�����n�b�`����͓��ɓ����H��������
MAD�ς����͒T�m�p�̋@�̂ɕK�v�Ȃ̂͒Ⴂ���q���x�ƍq�����������Ȃ��E�E
��햖���ň�Ԃ̖��́A�ǂ̋@��ł���ݑ��ȏ����@�́A�G�퓬�@�Ɍ��������炨�I�����Ƃ�������
>>632-634 ���X�Ƃ��Ċ������������AAC-130���ڂ̃{�t�H�[�X40mm�𖢂��Ƀ|���|���C�ƕČR���Ă�ł�悤�ɊC�R�̖��c���c���Ă��
�}�����q���̋@�e���[�Ɋւ��Ă͓��{�R�ł������߂Ă��̂܂ܐ���
�܂������N�̓j���J���Ղ���N����������������
>>633 �_�_���킩���ĂȂ��̂Ȃ炢����������ł��Ȃ��Ă�����
�V�[���[����A���D�c�h�q�̂��߂̑ΐ����ɂ��Ęb���Ă邾��������
>>637 pom pom guns�ŃO�O�b�Ă����B�b�J�[�X���̂�����o�Ă��Ȃ����H
�B��{�t�H�[�X���o���y�[�W�ł́u�|���|���C�̑�֕i�v�Ƃ������t���q�b�g����
>>638 �ΐ����̘b���Ă�̂ɋ��P�g���͂����ۂ�_�B�ۂ��o���Ă�������
��q���Ɗ��Ⴂ���Ă�̂��Ǝv�������H
>>636 �u���C�p�f�C�A�͍d�߂���
>>635 ����@�͗���@�ɔ�ׂĎx�����\�[�X�Ƒ��Ղ������߂���
96���͍U���Đ��Y�ʼnh�ƍP���y���ڂ�����
�q�������Ƃ����P���Ȃ����H
�\�V���Q�̂����ۂ͑ΐ��U���ł��邩�犨�Ⴂ�������w
93�����ԃg���{��6000�@�����Y����Ă邩��
�ꉞ�����ۂ͖����ɑΐ���ꂪ�K�v�ɂȂ��ĉ������ĎO���A���@�̔����͂��ł���悤�ɂ���
�ǂ����ő���93��������ΐ������@�Ƃ��ĉ^�p�����悤�ȋL�q���������Ƃ�����������
�u�C���q��v��931��̋㎵�͍U12�@��ΐ������p�Ƃ��ē��ڂ����A�Ƃ̋L�q�����邻��������A���̒ʂ肶���
>>632 �P�@�ŏ�������o���@����
�S�O�����{�t�H�[�Y�ɂ͂����������
�����U�{�[�g���ꎞ�A���[�_�[�Ŕ���������q���Ԃɍ���Ȃ�/���q���Ă������U�������̂ŁA20mm��37mm��C�݂��ď����@�ƑΌ����Ă���
453��̗뎮���㎥�T�����@�̑ΐ��{���͑��2�@��3�@�őD�c�t�ߊC�ʂ�{�����Ă���
��シ���ɐ��E�ōŏ��ɋ��Q�T�m�@��ʎY�o�������Ȃ���
���Q�T�m�@�́A�ΐ��p�Ō����쒀�͂������Ŏg���A�N�e�B�u�\�i�[�̗ނ���
����Ȏ��������烌�[�_�[�͔��A���e�i�����o�̓}�O�l�g���������{����s���Ă�
���������̂̓K���p�S�X�Ƃ͌����ȁB
�A�z�������͕��y�������ăA�h�o���e�[�W�������Ȃ鎖����w
���ɑ��闋�d�A�ɑ���w����
>>643 �upompom�v���C�R�X�����O�ő�@�֖C�̈�ʖ��������Ă邱�Ƃ��m��Ȃ��̂��c
�������͂��ꂩ������ė����A���̓j���J����
>>645 �_�B�ۂ͊C�R�͐����v�Ɋւ���ăJ�^�p���g�����ڂ��ꂽ���Ƃ��m��Ȃ��̂�
���łɐ����q�������^���Ă��炦�Ă�Αΐ��\�͂͂����ۈȏゾ�����͂�
>>657 AC130�ɍڂ��Ă�{�t�H�[�X����p���Ǝv���̂�ww
����f���悤�ɉR�����N�l��w
�_�B�ۂ̃J�^�p���g�͋����Ŕ�����������@�Ȃ���n���ۏo��w
�{�t�H�[�X40mm����@�֖C�Ȃ̂��m��Ȃ��Ƃ����W���ɔ]�݂�����Ȃ��ăS�~�ł��l�܂��Ă��
�_�B�ۂ̃J�^�p���g�͊C�R�̏d���y���Ɠ��^�Ȃ̂ɊC�R�͐�����킴�킴�f���b�N�ō~�낵�Ĕ���Ă��낤�ȁA�͂���~�̔]���X�͂���ς�S�~���Ȃ�
>>659 >>660 �ݓ��͌��ꂵ������������肾��w
��ˌ��Ɏg���Ȃ������C�Ȃ�ČĂԓz�Ȃ�ċ��Ȃ�w
�C�R�̊͂͊J�펞�ɂ�4t�܂Ŏˏo�ł���J�^�p���g�Ɍ����ς݂Ȃ̂��m���Ƃ�w
���m�ȃj���J�͂��O��www
�Ȃ�̂��߂ɏI��܂�94����Ƃ����g��ꂽ�����m���炵�����A�ˏo�@�P���̗��R���킩���ĂȂ����炱��������Ƃ背�X�����Ⴄ�낤�Ȃ�
>>662 �Q�[���]�̂��q�`���}�͐���@�͂�����ł������čD���ȕ����ڂ���ꂽ�Ǝv����������̂�w
����������@�̉^�p���тȂNJF���̋��P�g���͂ɐ���ڂ�����ΐ��ł���w�Ȃ�ĉ�S�Ȕ��z���邾���͂����ww
���O�̗c�t�̃I�c����p����100�NROM���Ă��w
1�b�Ř_�j�����o�J��ID:0QbEx6770
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9_40mm%E6%A9%9F%E9%96%A2%E7%A0%B2 ���{�t�H�[�X 40mm�@�֖C�i�{�t�H�[�X40�~��������ق��ABofors 40mm/L60�j�́A1930�N�㏉���ɃX�E�F�[�f���̃{�t�H�[�X�Ђ��J��������@�֖C�B
��l������ł��������Đ_�B�ۂ̃J�^�p���g�Ŏˏo�͖�������
�ꉞAC-130�̃{�t�H�[�X�A�Â��͒��ɍڂ��Ă���������]�p�����悤����
>>664 �\�[�X��wiki��w
����Ȃ̂͌R�̌ď̂ł��X�����O�ł��Ȃ����Hw
�ǂ���AC130�̑�ˌ����ł��Ȃ��{�t�H�[�X���|���|���C�ČĂ�ł��Ə����Ă����
�n�����������Xw
>>665 97�y�������d2.2���S��3.3������
>>666 �����ČR�̃{�t�H�[�X�����~����������̂ŃC�R���C�U�[�Ƃ��ɕς����
>>667 ���܂��K�`�̒m�I��Q�҂���
>>655 ���܂͎s�̂Ńh�b�v���[�����f�킪�����Ă���
��e�̕��̒��َ̑��̐S�����悭�������ďd�Ă�
�]�݂����E���R���ƌ�����Ȃ��낤�Ȃ�
https://books.google.co.jp/books?id=lbwfAAAAMAAJ& ;pg=PA781&lpg=PA781&dq=AC130%E3%80%80pompom&source=bl&ots=YRBK7TmHUE&sig=ACfU3U0JLspDaFOSX23Nq6aVknKYFwSL1w&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwj0w6WHiYLyAhWkGKYKHedVB3UQ6AEwD3oECBMQAw#v=onepage&q=AC130%E3%80%80pompom&f=false
�����̃{�t�H�[�X�̐����ɊC�R���́hpom-pom"�Ə����Ă����
>>669 AC130�̃{�t�H�[�X�̓|���|���Cw�����O�̔]���\�[�X�����甽�_���ł��Ȃ��ĉ������̂�ww
�Q�[���]�̔n���̒p���N��w
���q���̓G���R��35�~���@�֖C�Ƃ����X�{�[�����ē]�p���Ă�̂��ȁH
>>671 �\�[�X�̒�������m��Ȃ����m����w
������AC130���C�R�ɂȂ�����w
�撣���ĒT���Ă���ȓI�O��ȃ\�[�X��www
>>668 �i�[�ɂɓ���ĉ^��������Ȃ��́H
�ˏo�e�X�g�͂����ƌy���@�̎g���Ă邵
>>674 �g�����Ƃ��Ďw�E���Ă���肾�낤���S�Ăɂ����ēI�O�ꂾ��
�����Ɠ��{�̋`������������Ƃ��邩�H���_�a�F��ƍݓ��F�肵���Ⴄ��
>>676 �Ґ����˂Ŕ��_�ɂȂ��ĂȂ��I�E���Ԃ������Ⴄ�͔̂����l�̐��Ȃ̂��Hw
>>675 �ʂ̂���99�R���3t�߂����ˏo�ł��Ă�
���̊W�҂���ɑΐ������̑n�݂ɗ���ł�
>>678 ���ꂾ�Ǝˏo�\�̓M���M����CAM�V�b�v�݂����Ɍ�������������
�ΐ���������̂Ɋi�[�ɂ����ς��ɍڂ��Ċ�Ȃ��������ˏo������H�ڂɂȂ���
�������ɑI�����ɓ���Ȃ��Ǝv����
������C�R���琅��Ⴆ�悩�����̂ɁA�Ɖ��������Ă�
����@�͒�����Ɋ͂ɉ������̂���ԁA���̊ԂɑD�c�ɒu���Ă�����邩�A�҂��Ă��Ă��炤�����Ȃ���
�������ɂقƂ�ǂ̌��𐅒�͔����Ŏˏo�ł��Ȃ����낤
����@�̓A�����[�V�������瓇�ɔz�����Ă��g�Q��X���ŏ���ɉ��Ă�������
�_�B�ۂƓ����J�^�p���g����ʉ_�ǂ��납�뎮���コ���ˏo�ł��Ȃ������
1942�N�ɂ���Ɨ��R�^�A�i�ߕ����D���i�ߕ��ɉ��ς���đ�{�c�����ɂȂ����̂ɁA
96�����^����Ȃ�A�����͕n��ȃJ�^�p���g�ł��ˏo�ł����ł́H
>>685 95����^���K�@�Ƀt���[�g�t�����̂𗤌R�Ő��Y����
�Ƃ��������łȂ��́H
��O�����ʂɐ��Y���Ă�@�̂��ė��K�@���炢�����Ȃ����炠��𗬗p���邵���Ȃ���ȁB
�������߂āA�_�B�ۂ���j�����̏C���̍ۂɁA�����ۓ��l�̑S�ʍb�ɉ�������ق�������Ȃ�����
���X�S�ʍb���\��̖����D����Ԃ����ĉ������邭�炢�Ȃ�
�吼�m�ł͐��]�����o���������Ŗ��Ƃ�ɂȂ�
D-day�Ō}���ɏo��U�{�[�g�̑����͕Ԃ蓢���ɂ��������ǃV���m�[�P�������̊Ԃɍ������͂�
�_�B�ۂƌ`�����Ă������͑�~����ꗴ�P�ɉ������ꂽ�悤�ɁA�S�ʍb���͂��������Ɏv����
��~�͍ŏ�������ɉ����ł���悤�ɍH�v���Ă��͂�����y�ȕ���
�{���̓O���[�t�c�F�b�y�������~���������̂�
https://pbs.twimg.com/media/DsD3Hu3VAAABrgD?format=jpg& ;name=medium
��~�͍ŏ������s�b�ɂȂ鏊�ւ̃G���x�[�^�[���ݒu���Ă�����Ȃ̂ŕʊi�Ƃ���
�����ۑO���^�Ɣ�r���Ă݂�
�_�B�ۂ��㕔�\������⋭����ΑS�ʍb�����������Ɍ�����
�[��̈��V�ɐ��]�������Č������ꂽ�t�{�[�g�͑���
�[��̈��V����A�q��@�g���Ȃ�����
���q���̐��]���T�m���[�_�[�̓}�W����
>>686 �ϑ������낹�Ώd�ʓI�ɂ͂���2������
�u�G�����͌���I�v�ŋً}���i���͔R�����ڂ̕K�v���Ȃ������˂�����������Ƒ��₹��
�^�e�Ȃ�10�{
>>695 ��a�̉�����U���ɉ�q����������
>>699 ����SAR���J�����ꂽ���ɂ��������͂͐��]�����o���Ȃ��Ȃ���ăV���b�N���N����
���ꂩ���AIP�����������c��Ȃ����Ă�����イ�^�̊J���ɂȂ��������E�E�E
���ۂ͓�����CPU�̏����\�͂��ƊC�ʂ̈ꕔ������͂ł��Ȃ���������S�R�|���Ȃ�����
�悤����ɂ��ŋ߂܂Ő��]�������[�_�[�Ō�����͎̂���̋Ƃ������Ď�
�܂����������������Ƃ����ΒE������������
>>701 ����Ȏ��͒������̏��D�ɋ[���������
�����͂���J������~�Y�i�M�h�����U�������h���[���𓊎˂���
���݂ł����g����Ȃ���
���{�ɂ�����C���̐�����
����킾�ƕʂɐ����͂�����G����K�v������
�C��P�[�u���Ȃ��{�낤���債�ĉe��������
��햖���̌��ĕŁA�u20�~���̗̈́I�v�i��{�O�O�j�A�uP51���R���Ĕ�U�����v�i�ԏ��喾�j�Ƃ����̂����邪�A�M�ǂ̉��ǂňЗ͂𑝂��Ă��̂��ȁH
�ČR��12.7mm�ɂ��y���e����������A�}�e���y�������20mm���Ɗ��Ⴂ������������
��������20�~���͐퓬�@����Ȃ�\���ȏ�З͂�����B
>>709 �}�e���ė��R�ŗL����Ȃ��ˁH
�C�R���b��92�I�N�^���̐����@�ق��Ă����炢�����铽�Z�p�̗��C�R�̉��W�Ȃ�Ă���܂���ҏo���Ȃ�
�C�R�q����̂�13.2�~96mm�I�`�L�X�i�z�b�`�L�X�j�e������A�}�e�͂�����ʂ̞֒e��������
https://imgur.com/HNJHd9a ���I�N�^���R���̐��Y���@�͋����Ă��{���l�I�݂����Ȗ������������c����Ȃ��ƍ��Ȃ������
>>710 ���Ȃ͗��ɔ�e������
���̂܂ܗ��ʂ��y���y���Ɣ����ꗎ���Ēė������肵������������
���ꂱ���}�e���U�ʂɌ�������������
���ƑΛ������C�M���X�R�����X�Ɏg�p���~�߂�����Ă�̂��
7.7mm���e�����̃n���P�[���Ȃ珬�E���炯�ɂȂ���x�����ǁA20mm���ڋ@���肾�Ɣ��͂������㎵�d�����ꌂ
>>���ƑΛ������C�M���X�R�����X�Ɏg�p���~�߂�����Ă�̂��
>>717 ���̃x�e�����p�C���b�g�͂킴�ƃn���P�[����
�����Ƃ点�Ă��猂�Ă��Ă��
�܂��ɐ_�ƁA�C�X�p�m�S��̃n���P�[���͉��������
�������������炵��
�p�R�̓h�C�c�@�Ɛ���Ċi���Ɏ��M�������Ă�����ČR�ȏ�ɓ��{�@���r�߂č�����ɂ�����w
�u�ɍ~�����͑C�����ɑ��@�K�����������v�ƌ��������Ă��t�@���^�ꂪ�����Ƀf�^�������悭�����铮�悾��
���̑��x�ł��̊p�x�A���̍��x�ŏƏ��킩��ڕW���ꂽ�Ƃ���ŗ��Ƃ��A�Ƃ��P���ł��^�C�~���O�ł���Ă��
�_�C�u�u���[�L�̂Ȃ��퓬�����@���ƁA�}�~�������ł���Ȓ��ŗ��Ƃ������Έ����N�����Ȃ��̂ŁA�ɍ~���ł�邵���Ȃ�
�����Ƃ��n���P�[���͑�����ł͒������Ēx�����߁A�m���}���f�B�[�̍��ɂ��^�C�t�[���ɍ�������
�n���P�[�����C�O�h�L�������^���[�Ō����p�C���b�g���Љ�Ă��
�����h���[�X���ꂽ�\�A�̃p�C���b�g�ɂ͂���ȕ��Ɍ����Ă�
>>722 �t�B�����̓K���J�����Ȃ�ŋ@�������ɕt���Ă�
�����@�i�s�����ɑ��ĉ������ĂȂ��Ȃ��ʂ̏�̕��ɉf���Ă�O���̋@��
�ǂ�ǂ��̕��ɗ���Ă����͂������ǃs�b�^�����ɂ��Ă�
�悤����ɋ@����������ԂŔ��ł���Ď�
�����O�ɑO���̋@���@��������ďƏ������������瓊���O�ɉ�ʂ̉��ɍs������������
�n���P�[�����Ċz�ʂ��������炻�������y������������
>>728 �������炯�̃��X���Ă邯�ǁA�����v�H
���������ăt�@���^��̕�ID�H
>>730 ����ǂ����������Ă�̂��T�b�p���������
�O���̋@�͂ǂ����Ă��^��납�猩�Ă�p�����K���J�������Ə�̕��ɉf���Ă�
�@�������ĂȂ������炱��ȕ��Ɍ����Ȃ�����H
�@���ɍ��킹�ăK���J�������t���A���@�������������Ă���Ȃ�A�n�ʂ͉��ɗ���Ă������낗
���悾�Ƌ@���Ɛi�s�������قڈ�v���Ă�̂Œn�ʂ��قڗ���ĂȂ�
���e���Ƃ��܂ō��x�𗎂Ƃ������Ă�̂ɋ@������Ȃ킯���������
�@�������������Ă�����A��ʏ�̒n�ʂ͉��ɑ傫������Â��邗
����̓w���R�v�^�[�݂����ɁA��������Ă邯�ǐ�����s���Ă�ꍇ�����
�܂��܂��t�@���^�W�[�ȃ}�j���[�o�����ɂȂ�Ƃ�����
���������ɖ������炯�Ȃ̂ɋC�t���悗
����ȋO������}�~�������͂����Ɩ������킗
�@����������ɂǂ�����č~���������s����̂��HCCV�@�����ł���q��@���������炠�����Ƃł��H
>>735 �R�N�s�b�g���猩���ڕW�ʒu���ς��Ȃ��悤�ɏ����Ă݂�Ε�������
���x�@�������Ă邾���Ȃ�قƂ�Ǘ���Ă�悤�ɂ͌����Ȃ��Ǝv����
�}�~�������Ȃ琔���Ԃ����č��x5000�`7000�������肩��ɍ~���œ����āA���x2000�������肩��}�~���ɂȂ邾�낤���ǂ�
>>721 �̓��撆��10�b���x�̒Z���Ԃɂ������������ȋ@�����s���Ă��Ȃ��͈̂�ڗđR��
Sa5d-bSA8�͍~������ƃs�b�`���ς���ċ@���������Ɗ��Ⴂ���Ă�̂��H
���ɔ��Ƃ����x���オ��Ɨg�͂����������āA�����ɔ�т����Ă������Ă��܂�����A����[�������Ȃ��ƍ~���U���ɓ���Ȃ�
>>743 WAR Thunder wiki�ɑ������Łu���ۂ͏d�ʂ����������ɂ��ւ�炸�A�O���͑��x�ቺ���Ȃ��A�˂����݂��ǂ��ƍ��]���������B(�n�ӗm��w��̋Z�p�x���l��NF���Ɂ@2010�N3��)����1�v
���Ă��邯�ǁA���̗����Ō����Ώd����(�Ƃ܂ł͌����Ȃ��c)�̈��������ɋ@��20�Z���`���L�тăf�u�������O�^���͑ʍ�ǂ��납�d���Ȃ������ŋt�ɂނ�����ō��̔����������������Ȃ�
���͋@�瓷�̂���C�ɍi�肷���Ă銴�����邵
���̉h�̓n115���M���P�[�X���߂��Ⴍ���ᒷ���B
���ꏉ���̃n25-�h12�^�ƑS���̐L�т��n115-�h21���r���Ċ��Ⴂ���Ă��ˁHw
>>742 ����͉����t�@���^��ɔ��_���Ă��邱�ƂƂ͏������Ⴄ��
�t�@���^��͊ɍ~�������ł��˔��Ə���̃T�C�g�ɖڕW�����܂���x�ɋ@���������ƌ����Ă��������
>>748 ���O���e���Ƃ����ɖڕW�����ĂȂ��Ǝv���Ă�̂���w
���̂��߂̎˔��Ə���Ȃ�ww�n���Xwwww���O�̃I�c�����t�@���^�W�[����w
�܂������̃\�[�X���o�����_���I�������ł��Ȃ��m�b�x��̕��̍r�炵��
>>750 ���O���˔��Ə���͏��肾�����Ă����\�[�X�o����w
�����Ŏg���Ȃ��̂Ɏ˔��Ȃ�Ė��O�ɂ���̂���w��������ˁHw
�����ɜa��11�^�A���_�A���C�Ŗڐ�����Ō������̋㔪����^�A��͂ŎO���ꍆ��
�ɍ~�������ŏ\��
>>747 �����h�̍��͍��x�̓G���W���}�E���g������蒷��
��ɓ��̎���ŋ�C��R�����̕������Ȃ���Ȃ����Ǝv��
�a���͈ӗ~�삾��
���㔼�̃��[���b�p�ł�Ju87D���_�C�u�u���[�L��P�����Ė�Ԕ����ɐ�p�ύX�A�ĉp�\�͐퓬�����@��P���@�ɂ��ɍ~��������P�b�g�e�U������A
>>755 �X�J���C�_�[���ėm��Ŗ��q�ɂȂ�����ǂ������E�E�E�H
��͂��d�g�o���Ă����A���������T�m�@�i���{�R�ł͖����A�����ʑ���@�A�N���V�[�j�ŕ��ʂ����ł���̂ł́H
�D�̒����ɖ�����������o�C�^���p�[�g��j�ӂł���800kg�O�b���e�����ċ}�~�������ł���@�̂��J�펞���炠��ΐF�X�ς������������Ȃ�
97�͍U�ɉΐ��ς�ł��܂��̂�����
���d�͎���^�̃y���̑�^���ŏ������Y�ŏI��
>>760 �㎵�͍U�ɉΐ����œV�R
�����嗤�ɋ��͔����ŋ�㎮�P���@�Ȃ̂ł�?
>>754 GeeBee���[�T�[�݂����ɓ��̂�Z�k���ĕ\�ʐς����炷�����S�@��R�͌��肻���Ȃ����Ȃ��B
���21������32�ŃJ�E�����O�̌`�����P���ꂽ�̂��`���R�����ɗL���������Ƃ͎v���B
�L77�ŃJ�E�����O�`������P����̂Ƒ咼�a�y����ᑬ�ʼn��߂�
>>756 ���_�C�u�u���[�L�t���̋}�~�������@�̏o�Ԃ͖w�ǖ����Ȃ��Ă��܂�����ŁA���Ⴀ�ڕW���Ə��ł�������������Ȃ牽�ł����������|�I�Ɏ嗬�ɂȂ����A���Ęb
����̓��[�v�������������Ȃ̂��L���͂������̂��A�j���J������^�₾�ȁA���x�������ς�
�Βn�ƑΊ͂ł͖ڕW��F���ł��鍂�x���Ⴄ�̂ŁA��r�I���}�~���������n�߂�u�Βn�U���v�@�̂Ȃ�_�C�u�u���[�L�����ň����N������
���{���R�ł�97�y����99�P���@�������A1000�`3000�������肩�玸�������ċ}�~���������J�n������@�ōs��ꂽ
���C����^�̃t���b�v�ƃX���b�g���̍i��ŊԂɍ������x�̔�r�I���̋}�~�������J�n������
����ȏ�̍��x����̋}�~�������ł̓_�C�u�u���[�L���K�v������
�������x�����x�����[�v������s���ȓW�J��߂Ă���
����ƃX�c�[�J����̃_�C�u�u���[�L�P���́A�������ΐ�Ԏˌ�����ړI�ɂȂ������Ƃ��傫������
>>748 �ڕW�������Ȃ��̂ɔ��e�𗎂Ƃ��Ƃ��{�C�Ŏv�����́H
�펞���ɔ����ڕW���ԈႦ��m�����₽�獂���ČR�͓�������Ă��Ƃ����̂�
�������ʼn^���e��K���ɗ��Ƃ��Ƃ��푈�ɏ��Ă�킯�Ȃ�����E�E�E
����[���b�p�ł̐퓬�����@�͋}�~�������Ȃ��Ă܂����H���ɒP���@�œ��̒��S�ɔ��e�𓋍ڂ����ꍇ�A
����E���Y��������_�C�u�u���[�L��P�������P���@�d�l�A�����r�C�ǂ�t���Ė�Ԕ����p�ɂȂ���D-5�^
https://www.deviantart.com/drueobdianela/art/Junkers-Ju-87-D-5-873858843 �����ē����̑Βn�U���̎�͂́A�ߋ����P���@�d�l��Fw190F��A�����������^��Fw190G�ɂ��ɍ~�������ɂȂ�킯��
�O�l��������{�ꉺ�肭���Ȃ̂��I�H���Ă��炢�ςȕ��͂Ō떂��������_�_���炵�����o���ĂȂ����_�ʼn��̏����ŏI��肩��
�z���g�A�O���@�ɑ��鋻�����m�����Ȃ����Ă킩���
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1620344980/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��BTOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
Youtube ����
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜 ���u�y�ŋ��z���d/���d��22�y�퓬�@�z YouTube����>4�{ �j�R�j�R����>1�{ ->�摜>20�� �v �������l�����Ă��܂��F�E���q���Ɗ؍��ŌR�������ǂ��������́H ��_���ꒆ�����ĕ]������X���i�ȁj �E�N���C�i�289 �����}�ނł������ǂ�͊O�H�ɂčŋ� �����}�ނł������Ԃ͂��܂�c����Ă��Ȃ� ���ˈ߈��̎����T�܈�َ������˂��܂��� �E�N���C�i�142 �����}�ނł������Ë@�������Z���^�[�ł� �����}�ނł����ʔ��Ԏ�蕨���ł� �����}�ނł����A�f���[�A�J�����X �E�N���C�i�283 �I���^���I �P�܈������ۂ̌����莫�X ���Z�}�ނł��������������o���܂��� C-2/P-1�A���̔h���^�����X���ʎY196���@ �{��x�̖ϑz�X���b�h�@���\��b �����͍g�c���k�g�Ђ� ���U�@�̊ԈႢ���l�b�g��{�Ŗ������Ă�����B �y�T�E�W�z�h���[���ɂ��U�� �����}�ނł����_�[�N�G���t��A��ė��� �o�g��360�`���G���^�[�v���C�Y�̐킢�` #1�`5 ��q�͑����X���@Part.177 �`������Œj�q�͒���3�N�A���q�͉��3�N �y�ŋ��z���d/���d��26�y�퓬�@�z �����}�ނł������R�ł� �E�N���C�i�E���V�A� 1057 �����}�ނł����ʂ�o�[�o���[�}���Q�� ���{�����͑����X���b�h 100�Ԋ� �E�N���C�i� 342 ����}�ł����A������ȋ����[�I �����}�ނł����~������܂����܂ł͂ł� �؍������Ń~�T�C�����˂����O�@�m�\�Ȃ̂��H �e�q���ɂ��Č��X����6SS�R�x�t�c�m���g ����}�ނł��������ȑΐ�Ԓ�g���ʍU�����ł� �����}�ނł����鐭���V�A���A������߂Ȃ��B �E�N���C�i� 590 ����}�ł������׃��P�b�g�Ŏx�ߖŗ�ł� �E�N���C�i� 535 �A�T���g���C�t���X���b�h ����62 �����}�ނł����L���̖��M������ �E�N���C�i� 487 �����}�ނł���10�N�O�͖��ł��� �yF35B�͍ځz�������^��q��161�Ԋ́y�w�����z ��a�̑D�̂ƕ������g����50���g����͂���肽�� �����}�ނł����ً}���Ԑ錾����X�����Ă��܂� �y�y��ꉻ�z�������^��q��150�Ԋ́yF-35B�z �R���Z�������B�ƌ��ӂֈЂ��������k �������Ď��q�����R���ɂ���ƁH [�ꓙ���c��]���ь����X�� �����}�ނł����R�{�̃v�[�`���ł� �y�X�y���T�[�e�z���d�̍��̕��́y�����͂邩�z85 �����}�ł����X�����Ăł��܂��� �����}�ނł����n�����Î~������ł��B �y��ԁz�����{�R���b�ԗ������X���b�h Part.2 ���Z�}�ނł������X�g�I�u���U�W���ł� �݂}�ł����\�V���Q�ɖO���܂��� �����}�ނł����s���� F-35 Lightning II�@�����X���b�h�@98�@�� �yXF9-1�zF-3�����X��114�y����15�g���ȏ�z �����}�ނł������b�`���C�d�_�ł� �y���a���R�z��c�� ���ǎ҃X���y�i�c�S�R�z �y�N�[�f�^�[�z�@�I���h���u�n�k�ł͂Ȃ��j�������v F-35 Lightning II�@�����X���b�h�@72�@�� �ؼ��ى��z��L����ۯĂƌ�����]������X��18 �؍�KFX�����X�e���X�퓬�@�@Part12